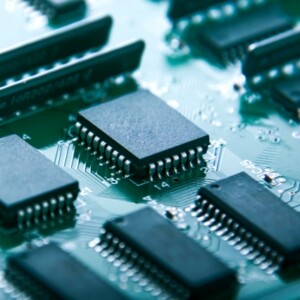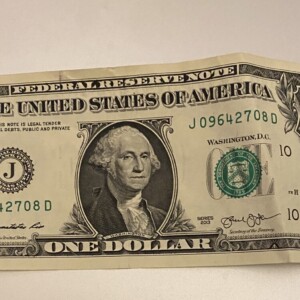三菱自、鴻海からEV 日産・ホンダにも続く「利益なき白物家電の轍」にハマるか
三菱自動車が台湾・鴻海精密工業から電気自動車(EV)の供給を受けるそうです。鴻海はアップルのiPhoneなどの受託生産で世界的電子機器メーカーとなりましたが、最近はEVにも進出。日産自動車副社長を務めた関潤氏をスカウトし、日産との提携を打診するなど急成長する中国勢を追撃する構えをみせています。三菱自は日産と資本提携しており、両社で軽EVを開発し、大ヒットさせた実績を持ちます。EVを鴻海から調達することをきっかけに日産を巻き込んでEVの品揃えを拡充する流れが生まれたら、日産・ホンダの経営統合協議にくさびを打つ格好になります。
EV提携の構図を先取り
読売新聞などによると、三菱自は鴻海からOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受けたEVをオーストラリアとニュージーランドで販売する計画しています。オーストラリア、ニュージーランドは人口が少ないこともあって自動車の産業基盤が小さく、完成車を輸入するか部品を現地で組み立てるノックダウン方式の生産が主体となっています。三菱自は東南アジアに次いでオーストラリア、ニュージーランドでも高い人気を保つブランドです。その三菱自でも2008年3月に現地工場の閉鎖に追い込まれました。
しかも、両国とも地球温暖化に対する国民的関心が大きく、オーストラリアは2025年1月からCO2排出量の上限を設定する新車販売の規制を開始し、自動車メーカーはEV投入が迫られていました。三菱自にとってあえて自社開発する選択肢はありません。自社の新車投入よりも、OEM先を増やしたい鴻海から調達し、まずは規制をクリアするのが得策と判断したのでしょう。
正直、鴻海のEVが三菱自の販売にプラスになるかどうかわかりません。EVは電気モーターの駆動系とバッテリーがあれば走るとはいえ、その実力は未知数、これからです。ただ、BYDをはじめとする中国勢の隆盛ぶりをみると、数年後には日本車メーカーに迫る、あるいは追い抜く可能性は否定できません。
BYDはすでに400万台を超え、米テスラと肩を並べる世界最大のEVメーカーの地位を確立。理想汽車などBYDに続く新規参入メーカーもここ数年で経営を黒字化し始めています。中国政府が世界最大の自動車市場である中国での拡販を後押ししていることもありますが、中国市場で積み上げた収益力をてこに世界へ飛び出しています。
待ち受ける中国勢と価格競争
中国を知り尽くしている鴻海ですから、同じ道を疾走する姿を容易に想像できます。三菱自にとっても、中国勢のEVに圧倒されて中国市場での苦杯を飲んでいます。日産、ホンダも同じ事情です。三菱自のOEM調達が軌道に乗れば、品揃えの充実を理由に鴻海と手を組む可能性は十分にあります。
しかし、危険な賭けでもあります。白物家電と同じ結末を迎える公算があるからです。1980年代、日本の家電製品は世界を席巻しましたが、韓国、台湾、中国による過激な価格競争に巻き込まれ、中国への生産委託などを増やしましたが、家電の開発力は急激に低下。日本製家電が世界市場から敗退する結末を迎えました。
EVはまだ普及期ですが、すでに白物家電で経験したコモディティ化が始まっています。中国勢が仕掛ける価格競争に抵抗できず、欧州メーカーの収益は大幅に悪化しています。日本車メーカーのEV開発・生産はまだ緒についたばかり。本格的な攻勢をかけるまでの時間稼ぎと割り切ったとしても、鴻海製EVは禁断の果実となる恐れもあります。中国勢のEVと価格競争で対抗できたとしても、過熱するコスト競争から逃れられず、白物家電の二の舞を演じるかもしれません。
日産とホンダは経営統合の協議を再開するかもしれないタイミングで、三菱自が鴻海からEVを調達するニュースが流れる事実をどう理解するのか。日産とホンダ、そして三菱自がコマと揃い、そこに鴻海が何らかの形で提携したとします。一見、世界競争に向けた体制強化に映りますが、近い将来白物家電が悲惨な末路を迎えたEVのコモディティ化が待ち構えていることも見落としてはいけません。