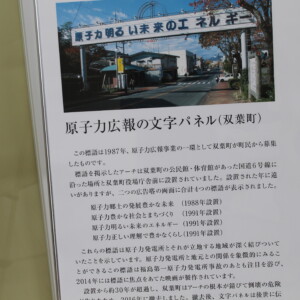米が安くなるわけがない 食管法の亡霊に翻弄される農水相、卸、消費者
失礼ながら、期待通りの失態でした。江藤拓農水相の暴言です。自民党佐賀県連のセミナーで「コメは買ったことはありません、正直。支援者の方々がたくさんコメをくださる。売るほどあります、私の家の食品庫には」。備蓄米の放出についても「価格が下がらない。大変責任を感じている。流通は難しい。たくさん出せば、値段が下がるというわけではない」。精米せずに玄米のままであれば備蓄米の流通を加速できるという趣旨の流れで語ったこととはいえ、昨年から倍も高いコメを買わされている消費者から見れば、とても笑えません。
備蓄米放出で値下がりはしない
期待通りと書いたのには訳があります。江藤農水相は資質を問われ、進退問題に発展していますが、35年前の出来事を思い出せば十分に予想されたことでした。
1990年の衆院選で江藤隆美運輸相が落選します。社会党の土井たか子委員長らのマドンナ旋風に自民党は吹き飛ばされ、江藤氏は現職大臣で落選。当時の運輸次官が責任を取って辞任すると述べるなど大騒ぎになりました。水面下で後継者として息子の拓氏を担ぐかどうかが話題になりました。
ところが、地元の宮崎県の支援者から上がる声は「あの器量ではとても衆院議員は務まらない」と悪評判ばかり。父親の隆美氏すら「息子には無理」と漏らしたそうです。運輸省幹部は「ありゃ本音だよ」と教えてくれました。江藤隆美氏は1993年の衆院選で復活。それから10年後の2003年、拓氏は継承者として衆院選で当選しました。
江藤農水相の資質を問うのが趣旨ではありません。言いたいことはただ一つ。江藤拓氏が備蓄米放出でコメ価格を安くできる仕組みを承知していたかどうかはともかく、農水省の役人にとって手玉に取るのが簡単な大臣だったということです。
石破首相ら政府はコメ高騰を鎮めるため、備蓄米放出を決断しました。だから、安くなるというわけではありません。大量放出で安くなると考えるのは経済原理が働いた場合。放出と言いながら、コメの流通はこれまで通り農水省の監視下のまま。事実上、統制経済の殻で守られているのです。備蓄米管理を指揮する農水省が戦前から握るコメを巡る既得権を手放すわけがありません。首相、農水相に対しては面従腹背といえるでしょう。
奇妙奇天烈摩訶不思議な世界
コメ流通の構造は、ドラえもんが歌うように奇妙奇天烈摩訶不思議な世界です。江藤農水相じゃなくても、農水省が描いたシナリオで備蓄米がコメ価格がどう変動するのか理解していたのは何人いたのでしょうか。備蓄米放出が話題になった時から疑問に思っていました。
備蓄米の放出は、政府がコメが不足したり、価格高騰した場合に備えて保管する米を市場へ流す制度です。集荷業者などが入札に参加し、希望する銘柄、数量、価格などを提示。最も高い金額を提示した業者が落札します。コメ価格への影響を抑えるため、原則として1年以内に落札した集荷業者から同じ量のコメを政府が買い戻すことも条件に加わっています。
気付きましたか。一連の流れはすべて農水省、米に関連する集荷業者などで占められており、新規参入など外部は事実上締め出されています。実際の落札が証明しています。備蓄米は21万トン余りが放出されましたが、JA全農が20万トン近く落札。JAの流通ルートでコメ卸売業者に販売されますが、 流通量は落札した量の4割ほどしか出回っていません。
しかも、コメ卸売業者は、外食チェーンなどへのコメ供給する契約を結んでいます。例えば最大手の神明ホールディングスは元気寿司など回転寿司チェーンを傘下に置いています。外食チェーンにとってコメの価格高騰は収益を圧迫しますし、なによりもコメが手に入らない事態になってしまえば、事業が成り立ちません。たとえ全農からコメ卸売業者に回ったとしても、外食チェーン向けの米確保が優先され、スーパーや小売店向けは後回しに。店頭に並ぶコメは少なく、価格が高くなっても不思議ではありません。
買い戻し条件も価格低下を妨げます。政府が買い戻す際、条件は同じ価格と同じ量です。集荷業者は落札した量をあらかじめ確保しなければいけませんから、先行きのコメ流通量が相当、過剰にならない限り、落札したコメ全量をすぐに販売するわけにいきません。1年後なら今年の作柄がポイントになります。直近で買い戻し条件の1年が5年に延長されましたが、全農に限らず誰も5年後の稲作の作柄を見通すことはできませんから、結局は集荷業者から卸売業者へ、そして卸売業者から小売店への流れが詰まってしまう。何の不思議はありません。
戦後も生き続けた食管法
コメの流通には戦前の1942年に交付された食糧管理法まで遡る必要があります。戦時中、コメは配給で統制されていましたが、戦後も食糧不足を解消し、国民の食糧を安定させることを目的に食管法は生き続けました。政府が生産者から米を買い入れ、消費者には安く売る仕組みを原則に需給調整していました。1980年代、コメ流通を取材して新聞に特集記事を掲載したことがありますが、食管法という堅城の中で農水省、農協、コメ卸売などが阿吽の呼吸でやりとりしている様には正直、驚きました。なによりも、農水省、全農などがコメ流通の混乱を歓迎するわけがありません。
1995年に食管法はコメ余りや食管会計の累積赤字などを理由に廃止されました。法律は消えたものの、流通を仕切る役者は変わりません。他に侵されない既得権は守るのが当然です。しかも、コメ不足に備える危機管理を名目に稲作農家の多くは農水省や農協の影響力から逃れることができません。稲作農家を支配した減反政策は2018年に廃止されましたが、農家経営はすでに疲弊しています。抵抗する力はどこにあるのでしょうか。
コメ高騰は、すでに廃止された食管法の亡霊に惑わされているのです。本気でコメ流通を改革し、価格を下げる覚悟があるなら、農水省の政策にとともに、全農や農協など日本の農業の根幹にメスを入れる必要があるのです。稲作などの農業政策、流通を理解するのは簡単ではありません。誰ができるのでしょうか。