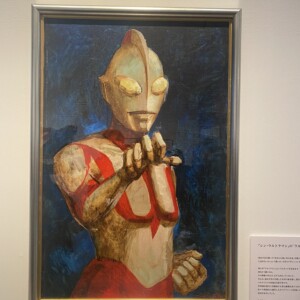ホンダが消える54「アフィーラ」ソニーと創る「三つ目がとおる」はEVを超えるか
「アフィーラ」。ホンダとソニーが開発する電気自動車(EV)を体感してきました。思わず浮かんだイメージは「三つ目がとおる」。その外観、人知を超える探知力を反芻していたら、手塚治虫さんのアニメ「三つ目がとおる」の主人公「写楽保介」が目の前に現れました。
見た目はおとなしく無邪気。平凡な中学生に見えますが、実は古代ムー大陸で文明を繁栄させた「三つ目族」の末裔。額に貼られた絆創膏を剥がすと、第3の目が現れ、超能力と天才的頭脳をもたらします。
一見、平凡だが超能力を秘める
体感したアフィーラの独創性を簡潔に説明すると、まさにこの通り。一見、どこにでも見かけるセダンですが、鍛え上げる「知能」はどこまで進化するのか。そして、その凄さがどうライバルのEVを圧倒するのか。興味が尽きないモビリティです。

ホンダとソニーの合弁会社ソニー・ホンダモビリティが東京・銀座で「AFEELA(アフィーラ)1」を公開しました。幸運にも開発スタッフから1時間程度、説明を聞く機会を得ました。試乗はできませんでしたが、ホンダとソニーが創り上げる「らしさ」、言い換えれば「どんなブランドに仕上がるのか」を考えてみました。
外観は2年前の2023年に公開したモデルと大きく変わっていません。ホンダ「アコード」をさらに磨き上げ、空気を切り裂く弾丸のイメージに仕上がっています。EVの弱点であるバッテリー性能に縛られる航続距離を伸ばすため、ボディの凹凸を徹底的に削り取って可能な限り空気抵抗を下げるのが狙いです。
なにしろ車重は2・5トン。EVは駆動系モーター、バッテリーを搭載するのでどうしても重量が増しますが、トヨタの大型SUV「ランドクルーザー」とほぼ同じ。これだけ重いEVが走るわけですから、車体表面もつるつるの滑らか肌に。
車体上部に突起3ヶ所
ところが、アフィーラのフロント上部にどう見ても空気抵抗低減の邪魔になる突起が3ヶ所。屋根中央部にはLiDARと呼ぶ探知機、左右部はカメラがそれぞれ内蔵されています。パッと見はまるで潜水艦の潜望鏡ですが、その機能はまさに潜望鏡そのもの。LiDARはレーダーやレーザーを使って周囲の状況を正確に探知し、歩行者、車両、他の障害物などを判断します。カメラは人間の目の代わりに周囲の状況を確認する補完的役割を担っています。
「アフィーラの性能を実現するためには、どうしてもフロント上部にLiDARとカメラを設置しなければいけない。空気抵抗をできるだけ抑えるよう形状の設計には苦労した」と開発スタッフは説明します。
空気抵抗を犠牲にしてでも設置せざるをえないのも、アフィーラの「らしさ」はこの高度な知能にあるからです。ホンダとソニーの共同開発車ですが、ホンダは走行性能を前面に出さず一歩譲って、ソニーが得意とするセンサー技術をフルに活用し、他のEVが到達できない「知的水準」をめざしているようです。。
アフィーラには車内外に合計40個のセンサーが配置されています。18個のカメラ、1個のLiDAR、9個のレーダー、12個のソナーが周囲360度を監視し、安全運転を保証します。ドライバーは運転席前のディスプレイで周囲をに3D映像で把握できますが、ソニーの高収益を稼ぎ出しているセンサー技術の方が信頼できるかもしれません。
レーダーの活用は大歓迎
レーダーやレーザーの活用は大歓迎。カメラを主体にした従来の安全監視システムは、土砂降り雨、濃霧、大雪によるホワイトアウトの時にはほとんど機能しない弱点があります。ドライバーが前方を全く確認できない恐怖の時にこそ安全監視システムがサポートして欲しいのに、カメラもその視力を失ってしまうからです。レーダーなら、雨や濃霧、大雪の悪天候でもかなり前方を探知でき、運転の不安を取り除いてくれます。

もっとも、レーダー、レーザー、カメラなど40個のセンサーが集める膨大な情報を処理して瞬時に判断する「知能」はそう簡単に創造できせん。レーダー、レーザーは反射する波を利用するので、カメラの場合では発生しない波長の干渉という新たな問題も加わります。ホンダとソニーは協業する半導体メーカーのクアルコムの技術を使って膨大な情報処理をこなし、アフィーラの学習能力を高めているそうです。
認識から推論へ進化するAI
ソニー・ホンダモビリティのHPでも「認識」から「推論へ」との見出しを掲げ、考える知能をアピールしています。走行している周辺を探知するだけでなく、周囲がどんな状況にあるかを推論し、安全で信頼できる自動運転をめざしているわけです。「世界でも前例の少ないレベルで『理解するAI』を実現するため、日々挑戦を続けています」と自らを鼓舞するのもわかります。
ただ、疑問は尽きません。どんなに優れた知能を体得したとしても、それがモビリティとしての魅力になるのか。カーレースのシミュレーションゲームを楽しむ体験に興じるならともかく、自ら運転しながら目的地に移動する楽しみ、ドキドキ感が失せてしまうのではないでしょうか。
アフィーラの魅力が高度な知能だけで表現されてしまうなら、むしろモビリティとして最も大事なものを置いてきぼりにしてしまう寂しさを感じます。
=次回に続く