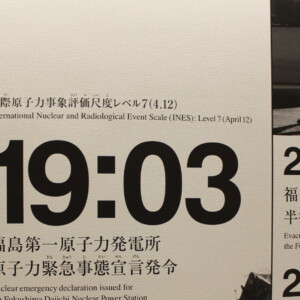日産、生き残りは自動車のTSMC 受託生産で経営再建はアリかも!
「その場しのぎ感」は拭えませんが、その場はしのげるかもしれません。日産自動車が相次いで受託生産するニュースが続いています。確かに日産の生産能力は世界が求める生産品質を保証できる優れた企業資産です。幸か不幸か、受け入れる余力は十分。
エンジン車から電気自動車(EV)へ自動車産業が大きく変貌している今、受託生産は世界の自動車メーカーが真剣に検討すべき選択肢の一つです。TSMCを思い出してください。1980年代、台湾で電子部品の受託生産を始めた中小企業は半導体の受託生産で世界トップクラスに。自動車で同じことが起こっても不思議ではありません。
ホンダブランドのピックアップトラックを生産
日産とホンダが日産の米国工場で生産したピックアップトラックをホンダブランドで販売することを検討しているそうです。ホンダはトランプ大統領が課す相互関税の影響で日本から輸出する車種の価格が割高になるため、米現地生産を急いで増やす必要があります。ただ、ホンダの米工場だけでは輸出の減少分を補えず、新たな増産体制の構築が急務でした。
日産の米工場は米国販売の不振で稼働率が低く、5割程度といわれています。ホンダからみれば、日産の工場を借用すれば自社工場に新たな生産ラインを設ける時間と金を省くことができます。
しかも、生産車種はホンダにとって品揃えが薄いピックアップトラック。米国ではセダンなど乗用車よりも高い人気を集めており、GMやフォードの収益頭になっています。日本車もトヨタ自動車と日産が頭抜けて高いシェアを握っており、中小型トラックでは米国車に負けていません。ホンダは4輪車では乗用車が主体であるため、トラックは後発組となり、手薄な車種です。米国で実績十分な日産製ピックアップトラックをOEM(相手先ブランドによる供給)で手に入れ、ホンダブランドで販売できればトランプ関税で先行きが不透明になった米国市場をテコ入れできます。
自動車業界ではOEMは珍しくありません。消費者からみれば、トランプ関税による値上げの影響を受けずにホンダブランドで日産品質のピックアップトラックを購入できるなら、大歓迎。
鴻海のEVを追浜工場で
日産は台湾の鴻海精密工業とEVの受託生産が進んでいます。閉鎖を検討した追浜工場(神奈川県)の稼働率を高めるのが目的です。鴻海の日本での販売計画が皆目わかりませんから、どのくらい日産の経営に貢献するのか判断できませんが、日産副社長も経験した関潤氏が鴻海のEV戦略を指揮していますから、ある程度のプラスは見込めるでしょう。
コロンブスの卵でした。日産といえば自社ブランドで販売する自動車メーカーという思い込みに縛られ、受託生産で経営再建する選択肢はぜんぜん思いつきませんでした。
冷静に眺めれば、確かに現在の日産が受託生産事業にシフトするのはアリです。2025年3月期に6000億円の赤字を垂れ流した主因は、世界販売の不振による工場の稼働率低下です。経営再建策として国内外で工場7カ所の閉鎖、従業員の大幅カットが発表されています。
裏返せば、工場の生産能力、ベテラン従業員の配置に余裕があり、それだけ受託生産できる能力があるわけです。
今度はベンツかVW ?
EVが壁に当たっているとはいえ、自動車メーカーはエンジン車、ハイブリッド車、EVと生産を使い分ける時代です。これまで世界の自動車市場をリードしてきた日本や欧米の大手は、EVへの巨額投資もあって生産設備や人員増を抑える方向です。
自動車は工場を建てれば、完成というわけではありません。生産ラインが計画通りに流れるかどうかをチェックすると共に、ミスなく作業できる熟練した従業員がどのくらい揃えられるかが勝負です。新たな工場建設、あるいは増産する計画を持っている自動車メーカーにとって日産の工場は十分に使い勝手があります。半導体産業では当たり前になっていますが、自動車産業でも車種によって自社工場、受託生産と使い分ける発想は大胆にコスト削減するためにも必須になるでしょう。
日産がホンダや鴻海以外にベンツやVWなどから受託生産する。決して絵空事ではないかもしれません。
◆ 写真は日産のHPから:ピックアップトラック「フロンティア」