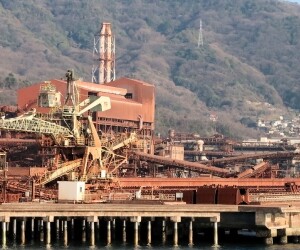トヨタ・ウーブンシティはレゴシティ? 社会実験は夢物語で検証できない
息子が幼い頃、ブロック玩具「レゴ」で車や電車を組み立てた後、ビルに見立てたブロックの街をクルマを握りしめて走り回って遊んでいました。ひとつ遊びを終えると新たなレゴブロックを造りたくなり、「あれも欲しい、これも欲しい」と言います。こちらは支払う財布に限りがあり、そんなにレゴは買えませんし、レゴシティを拡張する空間が自宅にあるわけがありません。「もう十分でしょ」。何度も「ダメ!」を繰り返し、諦めさせたものです。
豊田会長のレゴシティ?
トヨタ自動車は違います。財布の大きさは無限大。豊田章男会長が「街というよりは未来のためのテストコース」と呼ぶウーブンシティ構想は計画通り、膨張し続けます。ところが、冷静に眺めると、どうしても豊田会長が楽しむ「レゴシティ」に見えてしまう。いくら未来都市の社会実験をするといっても、蜃気楼を現実の街と重ねても実験結果は蜃気楼のまま。どうして気づかないのだろう。不思議です。
トヨタが9月25日、ウーブンシティの実証実験を開始しました。2021年から静岡県裾野市の工場跡地に建設を始め、第1期のエリアの4万7000平方メートルという広大な近未来都市が完成しました。トヨタ以外にの企業、その家族ら約300人が新住民となって生活します。毎日の生活は自動運転など交通システムや都市生活の進化を実証するデータとして活用されます。
ウーブンシティはその名の通り、多くの未来技術を織り込みながら(woven)、近未来都市の実証実験に挑みます。道路を見てください。自動運転のクルマが走るレーンのほかに1人乗りの小型の電動モビリティーと歩行者が共存するレーンが整備され、安全な新たな交通システムを研究します。ロボットがカーシェア用の車を先導し、指定の場所まで運ぶサービスもあるそうです。地下にも道路があり、ロボットが物流サービスやゴミ収集などの役割を負います。
絵に描いた餅は食えない
NHKによると、ウーブンシティの実証実験に参加する企業や個人は、「イベンター(発明家)」と呼ばれます。新住民一人ひとりが従来の常識に囚われずに安全に移動する新しいアイデアを考え、実現して欲しいと願っているのでしょう。自動車メーカーとして世界一のトヨタが建設した実証都市とはいえ、トヨタに染まらない織物を創造したい意欲を感じます。数多くの最先端技術を目の前に広げ、近未来都市をゼロから描き出すワクワク感を覚えます。
でも、それは「絵に描いた餅」。どんなに素晴らしい絵を描き出しても、「餅」は食べられません。
ウーブンシティに参加する企業はトヨタとのビジネスパートナー。都市の主催者であるトヨタの意向を念頭に実験を繰り返し、結果を捻り出すはずです。これでは社会実験になりません。実証実験とは、中立的な視点で繰り返されなければ有効なデータは得られません。実験手法に無作為と有意の2種類がありますが、ウーブンシティは有意抽出法に分類されます。 調査対象として特定の意図を担って参加するわけですから、調査結果の普遍性はとても低いはずです。
言い換えれば、ウーブンシティで得られたデータはウーブンシティ内で通用しますが、ウーブンシティの都市圏から出れば有効性は格段に低下します。
貧困世帯でも食糧よりテレビを買う場合も
社会実験はいかに難しいのか。比較して良いのか逡巡しましたが、ウーブンシティと同じ都市と地域を対象にした壮大な社会実験「ベーシックインカム」を例に実感してみてください。ベーシックインカムとは現在の社会保障制度と違い、年齢や性別、所得にか関わらずにすべての国民に一定の現金を無条件で支給する制度です。日本でも検討すべきと唱える政治家、政党が現れているので、ご存じの方も多いと思います。
ベーシックインカムを提唱するエステル・デュフロ、アビジット・バナジー両氏は2019年のノーベル経済学賞を受賞しましたが、「絶望を希望に変える経済学」などの著書でアフリカで数万人が参加する社会実験と通じて明らかになった驚きのエピソードを吐露しています。
ベーシックインカムは貧困世帯の救済が主目的であるため、一定の現金を得た人々はまず日々の食糧に費やす傾向があります。ところが、食糧を買わずにテレビを購入する比率が予想以上に高い結果も出たそうです。実験参加者を調査すると、飢えから逃れることは重要だが、多少の空腹感を我慢してもテレビを見ながら楽しい生活をしたいと考え、手にした現金をテレビの購入代金に回したことがわかりました。
デュフロ、バナジーの両氏は著書であまりにも予想外の消費傾向に驚きを示していましたが、読者の立場からみても空腹感よりもテレビなど娯楽が優先順位が高いことに驚きました。
ウーブンシティは貧困解消よりも、近未来技術の実証実験が主目的ですから、ベーシックインカムとは全く異なると考えるかもしれません。それは豊田会長が唱える「未来のためのテストコース」を走るモビリティの進化からみれば間違いがありませんが、実証実験の目的はモビリティを利用する人間との共存です。視点が全く違います。多くの人間が近未来技術と対峙した際、どう考え、行動するのか。100人単位、1000人単位の実験で検証できるレベルではありません。
ガリバーが迷い込む街は童話の世界?
小さな近未来都市を創造して、そこに住む人々がどう生活するのか。巨人ガリバーが見知らぬ街「ウーブンシティ」に迷い込んで驚く様は童話として面白いですが、それはあくまでも童話の世界。レゴシティを楽しむ子どもたちと同じです。