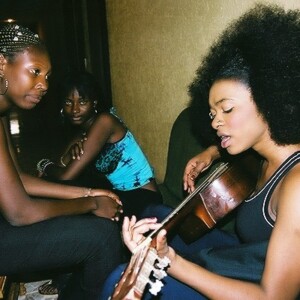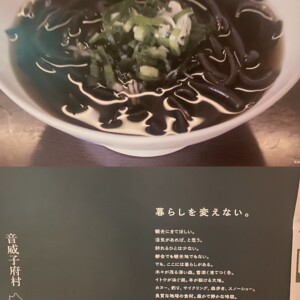「禁止」緊縛に陶酔する日本の美術館「だめよ、ダメ、ダメ」では魅力が半減
旅行に出ると、かならず地元の美術館を巡ります。訪れた土地に生まれ育った人がその個性と才能で創造するエネルギーを感じるのが好きだからです。いわゆる地物の魚や野菜、あるいは日本酒や焼酎を通じてその土地を知る体感とは違う「味わい」を覚えます。まだありました。美術館の建物も大きな魅力。美術館という存在が土地の風景をどう変えるのか、魅力を倍加できるのか。巨額の資金を投じて建設した自治体や住民、設計者の思いを推察するのが好きです。
「訪れて良かった」という感激はどこに
でも、日本の美術館でとても残念なことがあります。「禁止、禁止」に追い回されること。海外の美術館では写真撮影を禁止する例が少ないですが、日本国内ではまだ稀です。写真撮影を禁止する理由を理解しているつもりですが、館内に入った途端に「あれはダメ、これもダメ」と言われると、せっかく素晴らしい時間を楽しもうと意気込んできたのに萎えてしまいます。
「ダメよ〜ダメダメ」。2014年の流行語大賞になった日本エレキテル連合がオチで使うフレーズが渦巻く美術館もあります。入館料は安くありません。払ったモトを取るというわけではありませんが、入館者が帰る時、「高かったけれど、やっぱり訪れて良かった」と納得する展示を心掛けて欲しいです。
最近、がっかりした美術館はイサムノグチ庭園美術館。1999年の開園すぐに初めて訪れました。その時の感激を家族にも体感して欲しいと思い、久しぶりに香川県高松市へ向かいました。瀬戸内海にはベネッセの地下美術館や草間弥生さんの「南瓜」がある直島がアートの島として海外でも知られていることもあって、世界的な彫刻家であるイサム・ノグチさんの工房と住居を利用した美術館には多くの外国人観光客が集まっていました。
庭園美術館と名付けている通り、屋外展示が中心。イサム・ノグチさんの作品や制作途中の”石”などが多数展示されているほか、工房や住宅が当時のまま保存されています。主人のイサム・ノグチさんがニューヨークなど他のアトリエから戻ってきたら、すぐに使える空気を今も大事に保全するのが方針のようです。
20年以上も前は、とても自由に歩き回ってガイドさんとおしゃべりしながら、イサム・ノグチさんの生前の空気を想像した記憶があります。写真撮影も問題ありませんでしたし、作品に触れて人間の肌と変わらぬ優しさとエロスを感じることもできました。
イサムノグチ庭園美術館は「触っちゃだめ」
ところが、今回はガイドさんとのコミュニケーションがうまくできません。まず、写真は撮影しないでくださいと言われ、説明も極力、抑えていました。フランス人の観光客が多かったためか、フランス語の通訳さんと話しているだけ。美術館の目玉である工房に展示されいる作品は、出張中。
一番驚いたのは、屋外に展示している彫刻に触れたら、「石が劣化するので、触れないでください」とある入館者が注意されているのを見た時です。イサム・ノグチさんの作品はニューヨーク近代美術館、広島市の原爆資料館近辺の橋の欄干、札幌市の大通公園にある滑り台、さらにモエレ沼公園などを訪れ、きっと数多く見ていますが、いずれも人間が日々の営みで利用することを前提にしている作品です。
欄干がある橋は毎日、車、自転車、人が行き来するので、当然痛みます。大通公園の滑り台は子供も大人も一度は滑ってみたくなる魅力を発散しているので、遊具に。私も何度も滑りました。イサム・ノグチさんの作品は市民生活に溶け込んでいるのです。
それが「石が劣化するので、触れないでください」とは? 屋外に展示されているのですから、風雨にさられています。イサム・ノグチさんは自身の作品が自然や人間生活と共に変化することを承知していたでしょうし、期待していたのではないでしょうか。イサム・ノグチさんの住居も中には入れません。覗くだけ。イサム・ノグチさんが生前、工房や自宅で過ごした雰囲気をわずかでも体感できるでしょうか。20年以上と事情が変わって単純比較すべきではないとわかっていますが、庭園美術館の方針は魅力を半減しているとしか思えません。
もっとも、一緒に見学したフランス人観光客は写真を撮ったり、触ったり。ガイドの日本語説明はよく理解できないという空気が流れています。日本の美術館ではあるあるネタかもしれません。
もっとワクワクする美術館に
今回の旅行では倉敷市の大原美術館、直島の地下美術館などを歩き回りました。どこも禁止事項が列挙されます。展示方法も一方通行。「静かに見てください」という空気が充満しています。だからといって、鑑賞する立場を考慮して展示しているかといえば、そうでもない。絵画などを保護するためにガラス板が表面を覆っていますが、蛍光灯などで反射して作品全体を見ることができない場合もあります。展示されている絵画や彫刻は、オドオドしながら鑑賞する入館者を見て、残念がっているのではないでしょうか。