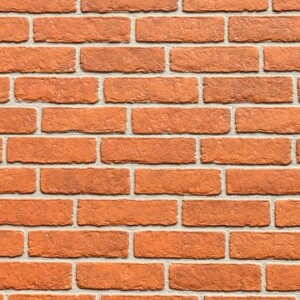ウエルシアとツルハが経営統合、めざせ「ドラッグストアのドン・キホーテ」!
ドラッグストア第1位のウエルシアホールディングスと第2位のツルハホールディングスが2025年12月に経営統合します。両社を合わせた国内シェアは25%を超えますが、それでも人口減で縮小する日本市場だけでは生き残れないと判断しています。経営規模の拡大によってめざす活路はアジア。経済成長が続き個人消費の伸びが期待できるうえ、調剤薬、薬品を購入する潜在需要がこれから広がると予測しています。
小売業態はスーパーと同じ
もっとも、ドラッグストアは現在の業態のままで生き残れるのでしょうか。店内は大きく様変わりしています。本来の薬品、調剤薬のほかに日用品や食品など幅広い商品が大きなスペースを占めています。野菜や魚など生鮮品を販売している店もあります。スーパーと変わりません。
ドラッグストアのライバルは同業他社どころか、スーパーやコンビニエンスストアと競っているのが実情です。そこにドラッグストア同士のチキンレースが加わります。互いに店舗網をどんどん増やして、ライバルと真正面から闘う消耗戦を繰り広げているのです。ウエルシアとツルハが経営統合して国内トップの店舗網と売上高を誇示したとしても、ライバルのドラッグストアのほかにスーパーやコンビニが加わって陣取り合戦と客を奪い合う現状を考えたら、国内シェア25%の威力は失せてしまうのは当然です。
しかも、本来業務の調剤薬ではネット通販の参入が本格化します。スーパーやコンビニが敵わない最大の強みである医薬品販売が足元から大きく揺さぶられているのです。ウエルシアとツルハの最大手2社ですら、国内市場に明日を見出せないのもわかります。
ウエルシアとツルハは活路をアジアに求めると説明します。日本のスーパー、コンビニはすでに中国や東南アジアで展開しており、業績の柱に育っています。ドラッグストアも日本国内での収益増が望めないのなら、アジアへと気持ちが向かうのは理解できます。でも、他を寄せ付けない業態を開発しなければ、結局は海外でも消耗戦を繰り広げるだけ。
日本のドラッグストアはどう変わるのか。薬局を併設しているとはいえ、日用品から生鮮品まで並ぶ混沌とした店内をはもはやドラッグストアとは名ばかりの小売業態?
「驚安の殿堂ドン・キホーテ」はモデルになりませんか? 店内の混沌さで比べたら、圧出陳列のドン・キホーテにとてもかないませんが、個性的な小売業態を創造するうえで参考になるはず。ドン・キホーテは創業当初、あまりにも雑然とした陳列に驚きましたが、店内を見て歩くと価格の安さにも驚き、「こんなものも売っているのか」と想像を超える品揃えの豊富さに何度も驚きました。
「驚安の殿堂」と自ら冠するのも納得です。しかもドン・キホーテは海外で大人気です。日本の店舗は海外の観光客で賑わい、積極的に店舗展開しているアジアでも好調な売り上げを記録し続けています。日本よりも高い評価を集めている印象です。これからアジアをめざすドラッグストアにとって羅針盤にならないわけがない。
差別化はドンキ+薬
めざす経営モデルは「ドン・キホーテ+薬」でどうでしょうか。さすがのドン・キホーテも調剤薬を店頭に並べるのは難しいでしょう。ちなみに近所のドン・キホーテはサンドラッグを併設しています。
ウエルシア、ツルハは元々、2027年に経営統合する方向でした。ウエルシアの親会社であり、ツルハの大株主であるイオンは、1年前の2024年3月にツルハの経営権を握った時に明らかにしていました。その後、米国証券取引委員会(SEC)の手続きが不要になるなどスケジュールを早めることが可能になったため、2年前倒しにしたそうですが、ドラッグストア業界の経営環境を考えたら、2年間も待っていられないとの焦りがあったと推察します。
処方箋は自ら試行錯誤するしか
ウエルシアとの経営統合を発表した記者会見で、ツルハホールディングスの鶴羽順社長は「アジアナンバーワンのグローバル企業への成長を目指したい」と話していました。その夢を叶えるためには、ウエルシアもツルハも自らの経営モデルをひっくり返すほどの荒療治を施す覚悟が必要ではないでしょうか。イオンはその処方箋は持っているのでしょうか。アジアでナンバーワンになるためにはどんな小売業態が望ましいのか。特効薬はありません。新たな小売業態の創出を期待しています。