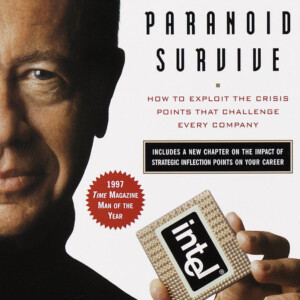下請けいじめ② キーエンス、強欲から目覚め、企業倫理の優等生をめざす
キーエンス。日本を代表する優良企業です。自動車、半導体、電子機器などの工場自動化ラインを支えるファクトリーオートメーションの部品を開発し、生産は外部に発注するファブレスメーカーです。事業展開は世界46ヵ国。経営効率を追求する実力主義の会社として知られ、社員の平均年収は2000万円超。営業利益率50%超える高収益企業として東証でも大人気。、凄いという言葉しか浮かびません。
ところが、「下請けいじめ」の視点に切り替えてキーエンスを見直すと、落第生寸前。下請け企業からの評価は散々でした。失礼ながら、金儲けには熱心な会社だが、企業倫理に無頓着。強欲に目が眩んだキーエンスと呼ばれても反論できる状況ではありませんでした。キーエンスの強さが企業倫理から見れば、裏目に出ていました。
強さの源泉は顧客志向の徹底
強さの源泉は営業の最前線。代理店などを通さず顧客企業と直接話し合い、生産ラインが抱える課題を解決する部品、システムを提案します。営業というよりは経営コンサルタントに近いかもしれません。現場で閃いたアイデアをもとにセンサー、測定器、画像処理機など数多くの製品・部品を下請け企業に発注し、素早く納入します。生産ラインの自動化に必要な部品は顧客仕様に設計されたカスタムメードですから、工場の生産性が確実に上がります。
もちろん、納入する部品の利益率は高い。社員の報酬は完全な成果主義ですから、頑張るだけ年収は増える仕組みです。顧客のニーズを汲み取り、製品・部品をいかに開発するか。製造業の勝利の方程式ですが、キーエンスの企業哲学として隅々まで行き渡っているため、キーエンスの高収益は止まることがありません。
もっとも、攻守の立場を変えて、キーエンスに部品や製品を納入する下請け企業の視線でもう一度、見直してください。かなり厳しい取引になります。キーエンスの購買担当者からみれば、顧客が求める部品をできるだけ早く、低価格で納入してもらうのがキーエンス流。下請け企業にとっては手強い相手。キーエンス社員は電子機器などの豊富な知識を持っていますから、自ら原価計算して下請け企業に発注するでしょう。「この価格じゃ無理ですよ」。常套句を使ってもキーエンスの担当者を簡単には騙せません。
2024年3月は最低の評価
案の定、キーエンスの「下請けいじめ」の評価はかなり辛い。中小企業庁が2024年3月時点の取引状況を調査した「下請けいじめ」では、下請け14社から改善して欲しいと指摘され、採点の平均点は価格交渉で「7点未満、4点以上」、価格転嫁で「4点以下、0点以上」となりました。
中小企業庁の調査は下請け企業が発注企業の取引状況を採点する方式で、平均値で「7点以上」「7点未満、4点以上」「4点未満、0点以上」「0点未満」の4段階に分けて評価しています。キーエンスの場合、価格交渉で4段階のうち上から2番目ですが、価格転嫁は下から2番目。といっても最低の「0点未満」と採点された企業は、タマホーム、エディオン、一条工務店ぐらいですから、キーエンスは事実上、最低評価に近いものでした。
下請け企業から見れば、キーエンスは価格交渉でそれなりに相手してくれますが、値上げなど価格転嫁は全く相手にされない印象を持っているようです。東証の株式銘柄でトップクラスの高収益企業と人気を集めながらも、高収益の源泉は社員の頑張りより「下請けいじめ」だったと思われたら、キーエンスの企業価値は落ちてしまいます。
正直いって、キーエンスは稼ぐことにしか興味がない会社と思っていました。もう30年近い前ですが、私が新聞で掲載した環境経営度調査でキーエンスの実像を見ていましから。当時から高収益企業として有名でしたが、廃棄物処理やリサイクルなど環境負荷の軽減には無関心でした。環境経営度調査は全上場企業に配布して、800社程度から回収しましたが、キーエンスは回答企業で最下位。環境経営にエネルギーを費やしても、何の得にもならないと割り切っている様子でした。
2025年は最上位の評価に
ところが、中小企業庁が公表した2024年3月時点の「下請けいじめ」で最低と評価されたことがかなり効いたようです。キーエンスは一転、生まれ変わっていました。
1年後の2025年3月現在の調査では「価格交渉」「価格転嫁」「支払い条件」ですべて最上位の評価。事実上の最下位から一気に最上位へ駆け上がったのです。実力主義が徹底しているキーエンスです。「下請けいじめ」の不名誉を一掃するよう徹底すれば、わずか1年間で成し遂げてしまうのもキーエンスでした。企業本来の評価は、収益力だけではないと気づいたのでしょう。強欲から目を覚まし、今度は企業倫理の優等生として株式市場の寵児になる日が近いはずです。