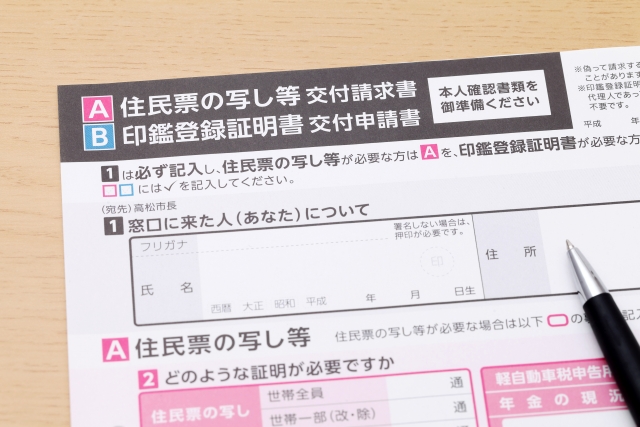
やっぱり市庁舎は不要!行政のDXモデル・北見市が新庁舎建設で財政難
やっぱり市役所の市庁舎は不要じゃないのでしょうか。自分自身が住む自治体がもう20年以上にわたって市庁舎建設が足踏みしており、つい最近になってようやく建設を正式決定。ここ数年の建設資材や人件費の高騰で建設費は計画よりも増えており、本当に竣工できるかどうか不透明です。なんとか完成したとしても、建設によって自治体の財政が悪化し、行政に影響が出てしまうなら本末転倒。
その実例がなんと北海道北見市で起こってしまいました。市庁舎の建設ができず、その代わり行政のデジタル化を進め、全国から注目されるDXのモデルになりました。その後、北見市は市庁舎を建設したら、財政危機に。市庁舎はいらない!。北見市が自ら立証したように思えます。
北見市の2050年は4万人の人口減
北見市は人口11万人の中堅都市。2006年3月に留辺蘂町、端野町、常呂町と合併して北海道で最も広い自治体となり、上水道、体育館、図書館など公共サービス・施設を管理・維持する費用が合併前と比べて20億円も増えました。公共施設の数は人口200万人の札幌市と変わらないというのですから、市財政の負担度合いは半端ないです。
にもかかわらず、2015年には35億円をかけて新しい図書館を、2021年には長年の懸案だった市庁舎を115億円をかけてそれぞれ建設しました。新市庁舎は高さ32メートル、7階建て。北海道新聞は「北見の街では異彩を放つ存在感」と表現し、市民の批判の声を伝えています。
現在でさえ施設管理などの負担が重いのに図書館や市庁舎の返済も新たに加わります。市の財政規模は歳入歳出ともに770億円程度。ただでさえ厳しい財政状況が悪化するのは目に見ていました。図書館も市庁舎も次代を担う若い住民にプラスなら、目先の財政悪化は凌げます。残念ながら、全国の地方都市で歯止めがかからない人口減が北海道でも札幌市以外の市町村に押し寄せています。北見市の場合、2050年までに4万人減ると予測されています。現在よりも4割近くも減少する計算です。
市の税収は落ち込むのは確実で、長期返済する市庁舎や公共施設などの建設費、維持管理は今まで以上に重くのしかかってきます。北見市が公表した財政状況によると、毎年30億円以上も財源不足となる見通しです。財政危機を乗り越えるため、公共サービスの縮小が計画されているそうです。新たなに開校する予定だった小中一貫校が白紙に戻ったほか、保育園の運営など市民の日常生活に直接関わるサービスが見直される方向です。
頼りのふるさと納税は過当競争
北見市が期待するのはふるさと納税。北海道の他の自治体がふるさと納税で大幅に増収している事例を念頭に税収増を見込んでいます。確かに紋別市は2023年度にカニなどの魚介類で200億円近くも伸ばしましたが、2024年度は返礼品のルール厳格化などで税収は大幅に落ち込んでいます。全国の自治体との過当競争による弊害も指摘され、ふるさと納税による財政の健全化はとても無理筋です。
自治体財政の悪化を招いたすべての責任を市庁舎建設に押し付けるわけではありません。「立派な市役所はあって当然」。市役所にも市民にも昭和から当たり前と思い、行政に対して疑問を抱かない感覚は令和の時代にもう通用しないことを思い知る必要があるのです。大きくて豪華な市庁舎がなくても、行政機能の分散化やデジタル化を進めて機能を特化した新市庁舎で十分に事足ります。
自治体の行政は常に右肩上がり。昭和に通用していた常識はもう時代遅れなのです。少子高齢化による人口減によって15歳から65歳未満の生産人口は1995年をピークに減少。企業誘致や移住などで人口や税収の増加を目論んでも、日本全体が成長していなければ自治体同士の奪い合い、言い換えればゼロサムゲームを繰り広げているだけです。
北見市がいち早く取り組んだ行政のデジタル化は、ほんの一歩にすぎませんでしたが、人口減時代を先取りした自治体行政の「令和モデル」でした。
令和の行政モデルを創る時
他人事ではありません。私が住んでいる地元も北見市ほど広域ではありませんが、人口はほぼ同じ。市庁舎の建設を20年以上も計画しながら遅々と進まず、ようやく着工する段取りとなっています。ただ、資材や労賃の高騰で建設費は計画を大きく上回るのは確実です。市長は基金の取り崩しなどで行政サービスの低下を防ぐ考えですが、すでに他の自治体ではあまりの建設費高騰で公共施設建て替えを断念する例が相次いでいます。とても楽観できる現況ではありません。
市庁舎建設に100億円を超える資金を投じるよりも、30年後の社会に合わせてコンパクトな行政をどう実現するのかを考え、次代を担う市民が担う社会や街を創ることに投資してほしいです。






