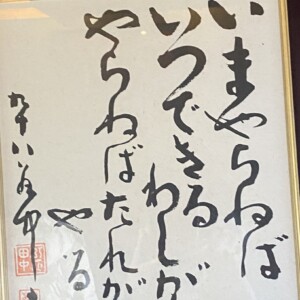昔は安宅、今はDIC川村記念 美術は破綻の沼?「大日本インチキ」の汚名晴らせず
DIC川村記念美術館が2025年3月に閉館しました。大手化学メーカーのDIC創業家の2代目社長、川村勝己氏が収集した400点近い現代美術は、日本企業のメセナ(文化・芸術支援)の代表例として高く評価されていただけに、とても残念です。引き金は最近流行の「物言う株主」の海外ファンド。経営効率を歪めているとの批判を受けて閉館に至りました。
物言うファンドに売却迫られる
果たして、美術収集は企業経営を破綻に導くのでしょうか。経営破綻と美術コレクションといえば40年近い前の安宅産業を思い出しますが、破綻の引き金は全く別。なによりもDICの企業ブランドを痛打する悪手です。結局は企業価値の低下を招く恐れがあります。どうも納得できません。
川村記念美術館は1990年5月、千葉県佐倉市に開館しました。モネやピカソはじめジャクソン・ポロック、フランク・ステラなど現代美術を収集。とりわけマーク・ロスコの抽象画7点を集めた「ロスコ・ルーム」は世界でも知られています。400点近い収集品の簿価は100億円を超え、美術市場に出れば1000億円を超えるというのですからコレクションの規模と価値に改めて驚きます。
もっとも、1990年の開館当時を振り返れば、川村勝己社長のコレクションの素晴らしさを素直に受け止めることはできませんでした。ある種の抗弁に映りました。開館10年以上前の1970年代後半に就職活動した世代にとってDICに改名する前の大日本インキ化学工業の評判は最悪だったからです。
大日本インキがアピールする企業イメージは輝いていました。「もうインキの会社じゃない。液晶など次世代の産業を創造する化学メーカーへ。君たちがやりたいと考える提案はなんでもできる会社だ」。
ところが、入社した先輩、同期から漏れる言葉は痛烈でした。大日本インキの説明を信じて入社したものの、社内の空気は旧態依然。創業家が殿様として君臨し、会社組織は年功序列で硬直している。「何にも言えない空気。大日本インキなんてもんじゃない。『大日本インチキ』と後輩には伝えたい」。聞いている耳が痛くなるほどでした。
その後も悪評がなかなか消えず、こちらも皮相浅薄な見方に縛られただけに 川村記念美術館の評価が高まれば高まるほど企業風土との乖離が心配になったものでした。2008年にDICと社名を変更した時も、これで「大日本インチキ」という悪名は消えるのだろうと思ったほど。会社の事業内容や決算の良し悪しよりも、川村記念美術館の存在がDICにとって企業ブランドを高める資産と見ていましたから。
その川村記念美術館を総資産利益率など経営効率の足かせと批判したのは香港の投資ファンド、オアシス・マネジメント。投資家の観点に立ち、決算書を分析すれば確かに一理あります。DICの時価総額は3100億円あるそうですが、その3分の1に相当する1000億円以上を美術品だけで占めます。
企業は事業収益で稼ぐのが本筋と説かれれば、総資産の3分の1が美術品という事実は歪です。しかも、美術館の維持費で年間数億円の赤字も出ます。2023年12月期で過去最悪の399億円の損失を計上し、海外の買収案件で失敗するなど経営がガタガタしている今は、株主、投資家が事業に専念しろと求めるのも至極当然です。
しかし、企業の価値は事業収益だけで計るものか。長年、企業取材していると、無味乾燥な決算数字で表現しきれない価値があると思っています。「この企業はなぜ、世の中に存続する価値があるのか」。投資ファンドのオアシスから冷笑されると思いますが、「会社はだれのものか」という視点を忘れるわけにはいきません。
安宅産業は世界的な陶磁器収集
40年近く前に経営破綻した安宅産業とダブります。創業家2代目の安宅英一氏が収集した中国、韓国の陶磁器コレクションは今、大阪市の東洋陶磁美術館で展示されています。国宝「油滴天目」など素晴らしい作品ばかりで、大好きな美術館の一つです。
安宅氏が欲しいと願った陶磁器を手にする凄まじい執念は側近の伊藤郁太郎氏が著した「美の猟犬」に描かれていますが、その迫力があまりにも逸脱しているためか、世界的なコレクション収集と経営破綻が裏表に重ねられて勘違いされている時があります。
安宅産業は1970年代、10大商社の一角を占めていました。陶磁器収集は確か定款に明記され、会社の財力があるからこそ収集できた世界的なコレクションであったのは事実です。
しかし、経営破綻は、三菱商事や三井物産の背中を追った一大博打ともいえる石油投資の大失敗にあります。当時の社長ら経営陣は国際詐欺まがいの契約を結び、それが命取りに。コレクションと経営破綻は直接関係がありませんが、陶磁器の散逸は日本の損失と注目されました。安宅産業は伊藤忠商事が吸収合併しましたが、安宅コレクションは住友銀行が面倒を見て大阪市に寄付。これが東洋陶磁美術館となります。
美術館も企業価値
安宅産業の経営破綻で苦労された社員の皆さんにはとても申し訳ないですが、このコレクションを残した安宅英一氏の慧眼には感服します。企業は消えましたが、安宅はコレクションとして永遠に残ります。これも安宅産業が創造した企業価値と受け止めるわけにはいかないでしょうか。
偶然にも、あるいは皮肉にもDIC川村記念美術館は、安宅産業と同様に創業家2代目が残しました。DICは徐々にコレクションを売却する方針だそうですが、散逸せずに残せば大日本インキは「大日本インチキ」と揶揄された汚名を晴らすことができます。そんな企業価値の継承を考える余地はないのでしょうか。