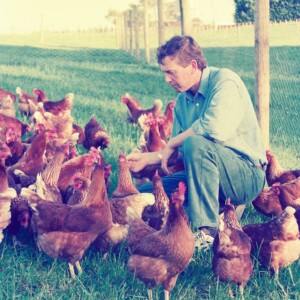令和の米騒動、乱高下、買い占め、農家の怒りが渦巻く 農業政策はぶっ壊れるかも
令和の米騒動が過熱しています。政府は備蓄米放出を入札から随意契約へ切り替え、米価格を現在の半値近い5キロ2000円程度に切り下げると言明しました。急激な高騰に苦しむ消費者にとって朗報ですが、出回る6月過ぎから新米が登場する秋にかけて店頭や流通が大混乱するのは確実です。小泉純一郎首相は「自民党をぶっ壊す」と連呼していましたが、息子の小泉進次郎農水相は自覚がないまま、農業政策の根幹である米の生産、流通をぶっ壊すかもしれません。
随意契約は風穴を開ける
まず割安な米は店頭に並んだ途端、買い占めが広がって瞬時に消えるのは間違いありません。5キロ2000円程度の放出量は30万トンですが、年間700万トンを超える消費量の5%にも届きません。小泉農水相は上積みして放出すると表明しているものの、品不足を解消することはできません。昨年夏、店頭で「1人1袋」の張り出しが掲げられましたが、同じ風景が再現するのでしょう。
安い米が消えた後、全農などが落札した備蓄米が2000円を大きく上回る価格で店頭に並んだら、消費者は当然、目を剥きます。一度、安い米を知ってしまった消費者は、店頭に再び並ぶ4000円台の米袋の山をどう見るか。「背に腹はかえられぬ」のことわざ通り、腹が空いて購入を我慢するのも限度がありますから、買わざるを得ないでしょうが、そのお腹は不満でパンパンに膨れます。
販売するスーパーや米店なども困惑します。2000円程度の米は1万トン以上を販売できる業者が随意契約できる条件です。すでに楽天やイオン、ドン・キホーテなど大手流通業者が手を挙げていますが、とても1万トンなど捌けない米店など小規模な小売店は事実上、締め出されます。安い米を販売できず、割高な米しか扱えない米店はとても苦しい立場に追い込まれます。小泉農水相は米店などに届くようにすると言いますが、複雑怪奇な米流通がそんなに融通が効くわけありません。消費者、小売店双方から怨嗟の声が湧き上がるでしょう。
参院選まで安価は続く
支持率低下が続く石破首相ら自民党は、米高騰を力ずくで解消して7月の参院選に臨み、なんとか帳尻を合わせるはずです。見た目はこれからの2ヶ月間をなんとか安値安定でしのいだとしても、新米が出回る秋以降は再び高騰の風が吹きます。
なにしろ、全国の農業協同組合はこの1年間の米高騰に合わせ、稲作農家からの買い取り価格を相次いで大幅に引き上げています。例えば、JA全農にいがたは2025年産コシヒカリに対し買い取り価格にあたる「概算金」の目標を60キログラムあたり2万6000円以上に設定しました。2024年産に比べ5割も高い水準です。政府の備蓄米放出後も全国で品薄が続き、米の争奪戦が激しさを増しており、文字通り青田買いの様相となっています。
概算金は米の流通価格の指標となります。コシヒカリの主産地である新潟が引き上げるなら、全国も追随するのは必至です。政府が価格引き下げで介入しない限り、現在の米流通に従えば、小売価格が上昇することはあっても下がることはないでしょう。
稲作農家にとってはなんとも複雑です。親戚の農家は長年、「いくら頑張っても、利益は出ない」と嘆いていました。概算金引き上げなどで農業経営の収益は改善し、ほっとひと息をつけますが、高騰によって米の需要が縮小したら、元も子もありません。
飼料米の作付けが大幅減少
農家の作付けも大きく変わり始めています。主食用の米が高騰しているため、飼料米などの作付けが減少する見通しです。日本農業新聞によると、2025年1月時点で前年に比べ16%減の8万5100ヘクタールとなる見通しで、1万3600ヘクタールも削減されます。飼料米で得る金額は主食用米に比べ1万円程度も違うそうです。日本の畜産業などは外国からの輸入飼料に大きく依存しているだけに、飼料米の生産縮小は日本の農業経営に大きな打撃となります。
石破首相は農水相を務めていた2008年末に減反政策の見直しを発言し、農業政策の改革に乗り出した人物です。食管法時代からの既得権を手放したくない自民党の農林族から猛反発を受けながら、次世代の農業にに向けて変革に立ち向かいました。
17年後の2025年。幸か不幸か、首相として米高騰によって足元から崩れる日本の農業をどう再構築するのかを任されています。まさか小泉農水相が打ち上げ花火のように演じる5キロ2000円台の引き下げ劇で終えることはないしょう。17年前の強い信念を思い出してください。