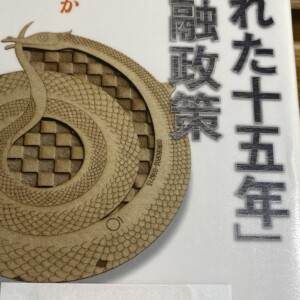「困った人」と「困らない人」を識別する「困った社会」独創的な個性を無駄にせず、活かす社会に
「困った人」が論議を呼んでいます。
書籍「職場の「困った人」をうまく動かす心理術」(三笠書房、神田裕子著)が差別助長しているとの批判されています。著者の神田さんは、産業カウンセラーとして職場で一緒に働く人とのコミュニケーションなどをアドバイスする専門家です。三笠書房のホームページによると、本書は「困った人」タイプをASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、愛着障害、自律神経失調症、うつ、更年期障害、適応障害、不安障害・パニック障害などに分けて対応マニュアルを紹介しています。
ASDなどの対応マニュアルが論議
この10年ぐらい、ASDやADHDなどが話題になっています。文部科学省が学校教育のあり方を見直すなど社会的な関心事として注目を集めています。本書の解説文では「困った人」に苦慮する経験として「なぜあの人の「尻拭い」をさせられるのか?」「あの人、いつも私に仕事を押し付けて、自分はふらっといなくなる」「どうして私だけが、損な役回りを引き受けなくてはいけないの?」といった具体的な事例を示し、「それぞれの言動や思考の裏側を解剖することで、戦わずして勝つためのテクニックを紹介します」としています。
正直、苦笑しちゃいます。困った人の事例いずれも自分自身に当てはまり、「どうして突然、姿を消すのか」「なぜ、そんなキレてしまうのか」などと職場で言われ続けました。今、学生時代を過ごしていたら、きっとASDかADHDと診断されていたのかもしれません。
社会的なトラブルも経験しています。私の子供が自閉症と診断されたこともあって、幼い頃から「親の躾が悪いから」と陰口を言われ、電車に乗っていると「いい加減、泣くのをやめさせろ」という厳しい視線を浴びたことは数えきれません。成人した後も、職場や通勤電車でいろんなトラブルに巻き込まれました。
だからといって、ASDやADHDなどの人間がいつもトラブルに巻き込まれるわけでもなく、引き起こすわけでもありません。「十把一絡げ(じゅっぱひとからげ)」、まるで血液型で人格や人生を占う感覚で、人間の個性を定型する発想にとても違和感を覚えています。日本自閉症協会が本書について「この本は表紙と帯、および目次をネット上で見ることができますが、それでも差別や偏見を助長すると判断する」と表明したのも頷けます。
「困らない人」っているの?
もっとも、「困った人」はいるけれど、じゃあ「困らない人」ってどこにいるのか。そんな疑問がいつも浮かびます。障害児の反対語は健常児ですが、自分の子供と一緒に育つ過程の中で「健常児とはどんな子供、大人なのだろう」と考えてきました。健常児は心身とも健康であることと定義されていますが、100点満点の人間なんかいません。どんな子供でも大人でも何かしらの悩みを抱えています。最近、子供らの現況をみていると、むしろ親や周囲の期待に応え、健常児の枠組みに嵌め込まれることに辛さを覚えているように思えます。新聞やネットで流れる社会事件を見ていれば、すぐに納得してもらえるはずです。
街を歩いて、見渡してください。「困った人」によく出逢いませんか。例えばペットの愛好家。公園や住宅街を愛犬を連れて歩いている姿を毎日、見かけますが、大小便を至る所に散らしています。拾ったりペットボトルで水をまいて後処理しているつもりのようですが、毎日、数えきれない愛犬家が歩道や公園の樹木の根元に便を散水されると、枯れてしまうのです。愛犬家同士が集まり、歩道や公園広場を塞いでしまうことも見かけます。みんな「健常児」のはずです。
本人に悪気ないのは承知していますが、公共財産を傷め、他の歩行者や公園利用者に迷惑をかけています。周囲に目配りや気配りができるはずの人々が、他人に「尻拭い」をさせているのです。
直近では花見でしょうか。満開の桜並木を楽しみに多くの人が集まりますが、場所取りにテントやシートを使い、桜の周囲で歩き回り飲食します。当然、桜に負担がかかり、最近はソメイヨシノの老木化が進み、倒木も続いています。にもかかわらず、花見の会と称した老人会のみなさんは桜の枝に幟を差し込み、枝や花を傷めています。桜は「なぜ私だけそんな役回りを引き受けなくてはいけないの」と泣いているかもしれません。
新聞社は「困った人」の集まりだったが・・・
極端な例ですが、かつて私が勤務した新聞社は「困った人」たちの集まりでした。原稿を書いたペンやタバコは床へ捨て、新聞編集を終えた後は大酒を飲みます。挙げ句の果てに喧嘩は日常茶飯事。宴会で取っ組み合いをして骨折した人もいました。「キレる」「突然、行方不明」「突然、怒鳴る」はもう慣れっこ。今で言えば、毎日がパワハラでした。
新聞記者は普通の社会で生活できない人たちがする仕事だと思っていました。それでも昭和から平成までは新聞は役立っていたはずです。「困った人」たちが集まっても、それなりの仕事はできるのです。「困った人」を手懐けるよりも、「困らない人」が持たない才能をいかに引き出し、新たな価値を創造することに精力を費やすのが本筋じゃないでしょうか。
「困った人」、あるいは「困らない人」に振り回される社会、組織は、無駄なエネルギーを消費しているとしか思えません。まさに「困った社会」ではないでしょうか。