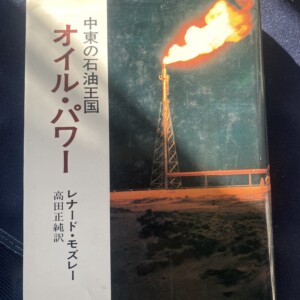70年前に西脇順三郎が嘆いた「肩書き社会」今も日本の変革を阻み続ける
西脇順三郎。詩人、英文学者、そして秀逸な絵画を残した多才な人物です。1894年に生まれ、1982年にお亡くなりました。慶應大学の小泉信三教授に師事し、同級生には後に共産党のリーダー野坂参三氏。理財科(現在の経済学部)に入学したにもかかわらず、英仏など多くの語学を使いこなし、卒業論文はラテン語で執筆します。信じられない。慶大文学部教授として英文学の教壇に立つかたわら、戦前日本のモダニズム、シュルレアリズムなど主導。彼の作品は1950年代、何度もノーベル文学賞の候補にもなりました。
英文学者、詩人、批評家・・・多才な人物
西脇さんが歌い上げる詩の世界が高校生の頃から好きでした。自由奔放に言葉が躍り、表現を纏う言葉も縛られません。言葉はまるで花火のように飛び散るのですが、すべての言葉には通奏低音として詩人の思いが染み込んでいます。
詩に登場するモチーフも多彩です。ギリシャ神話から登場した女神が現れたと思ったら、次の段落には日本の田園風景が広がります。時空を瞬間移動している幻想に惑わされますが、それが快感。詩人は読者に理解して欲しいなんてと思っていないのではないか。西脇さんが詩で作り上げる小宇宙を彷徨い、一緒に躍動することだけでとても楽しくなるのです。
彼の世界を知りたいと思い、この2年間、西脇順三郎全集(筑摩書房)を読み続けています。全部で12巻。膨大です。東京・荻窪の古本店で発見しましたが、「とても読みきれない」と思い購入を逡巡していたら、古本屋の店主に「全集すべてを読む人間なんかいないよ」と諭され、買ってしまいました。
全集は銀河系でした。詩の銀河もあれば、翻訳、批評、エッセイなど様々に光り輝く銀河が待ち受けていました。英文学者、詩人などの言葉の定義で収まらない活躍の場に改めて驚き、感動しましたが、西脇順三郎さんは日本社会に息苦しさを覚えていたようです。
肩書き社会を「日本風情」に
全集10巻に収められている「日本の風情」。短いエッセイですが、西脇順三郎さんは「日本の風情」の一つとして日本の肩書き社会について触れています。初めてお会いした時に差し出す名刺、あるいは新聞やテレビなどで紹介する時に必ず目にするのが肩書きです。肩書きを見て、初対面の人物を評価、値踏みするのが日本社会の常識です。
西脇さんはに肩書きに縛られる「日本の風情」の不思議と理不尽を簡潔に解いて見せています。一部を以下に引用しました。
日本では英国などに比すると職業、専門、肩書きなどを非常に尊ぶのは面白い。新聞雑誌などでカッコの中に入れて大学教授、詩人、批評家・・・・というように分類する。僕は、職業乃至専門として英文学をやっているが、英文学に関する随筆を描くと、(大学教授)と銘をうたれる。権威があるものとして読者はよむだろうというのが雑誌社のねらいらしい。
これに反して絵画の雑誌に画論を書くと、(詩人)と銘をつけて、「この画論を書いた人は専門の絵画批評家ではなく素人であるからそのつもりで呼んで頂戴な」といわんばかりである。
(中略)
日本では専門とか肩書きが有利である。名誉いうよりも経済的に必要なのであろう。玄人を重んじ素人を軽蔑することは全く職業意識からである。「なわばり」をきめるのである。英文学の専門家が仏文学の論文を書くと素人して排斥される。
僕が詩を描くと「おたのしみですね」といわれる、即ち「君は素人だ」というのだ。(中略)僕という大学の教員が詩を書くと素人になる。大体詩人は職業でないから玄人はいない筈だ。(中略)僕は若き小泉先生から野坂と一緒に共産党宣言を習った経済学生であった。だから、僕の英文学などは素人の芸術ということになろう。
名実ともに日本の文学・文化の頂点に立つ西脇順三郎さんが素人と呼ばれるなんてあり得ません。でも、文学のみならず社会のあちこちで独り歩きする肩書きの権威が新たな発想や若い世代の台頭を阻む現実を見逃すわけにはいかなかったのでしょう。詩とはアイロニー(皮肉)であると考える西脇さんですから、「日本の風情」を皮肉たっぷりに描いたのも納得します。
エッセイ「日本の風情」はほぼ70年前に発表されています。しかし、今も日本の肩書き社会は「なわばり」が存在します。
一度だけ「なわばり」が消え去った瞬間がありました。第二次世界大戦の敗戦によって日本の権威と秩序は焼き払われました。明治から継承された血脈や財閥はご破算となり、若くて才能がある人材が力を発揮する時代がありました。過去の栄光と実績を盾に封じ込める権威に阻まれることがありません。それがソニー、ホンダを生み、世界に躍進する新たな日本経済のエネルギーとなりました。
戦後、消えた「なわばり」が復活
残念ながら、「なわばり」に復権は早かった。三菱、三井など旧財閥系の企業はすっかり日本経済を牛耳り、政治も明治の復活と勘違いするほど長州閥を中心に息を吹き返します。
社会意識も「なわばり」にがんじがらめ。人物の評価は東大などの学歴、大企業名で定まり、研究論文の評価はそっちのけで大学教授の肩書きがあれば多くの人は耳を傾ける。新聞やテレビも含め、肩書きが説明する「なわばり」が現在の権威と秩序を仕切っています。そろそろ肩書きを捨て実力を吟味し、議論を深める時です。
日本は1990年代から30年間、経済成長も年収もなにもかも事実上ゼロ成長が続きました。1980年代、米国に次ぐ世界第2位の経済大国の座にまで上り詰めましたが、「なわばり」の湯船に浸る気持ち良さに酔い、「茹でガエル」に。ようやく危機意識が生まれ、変革を連呼しますが、「なわばり」はこれまで通り。これでは政治経済の停滞は続きます。GDPはもうすぐインドに抜かれて世界5位に下がります。トランプ関税など真面目に考えることに苦痛を覚える理不尽な出来事が多く、もう「なわばり」を日本の風情と眺めている余裕はありません。