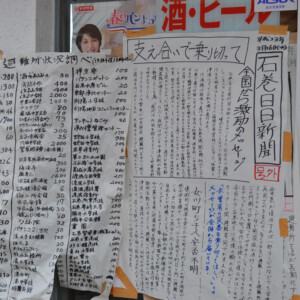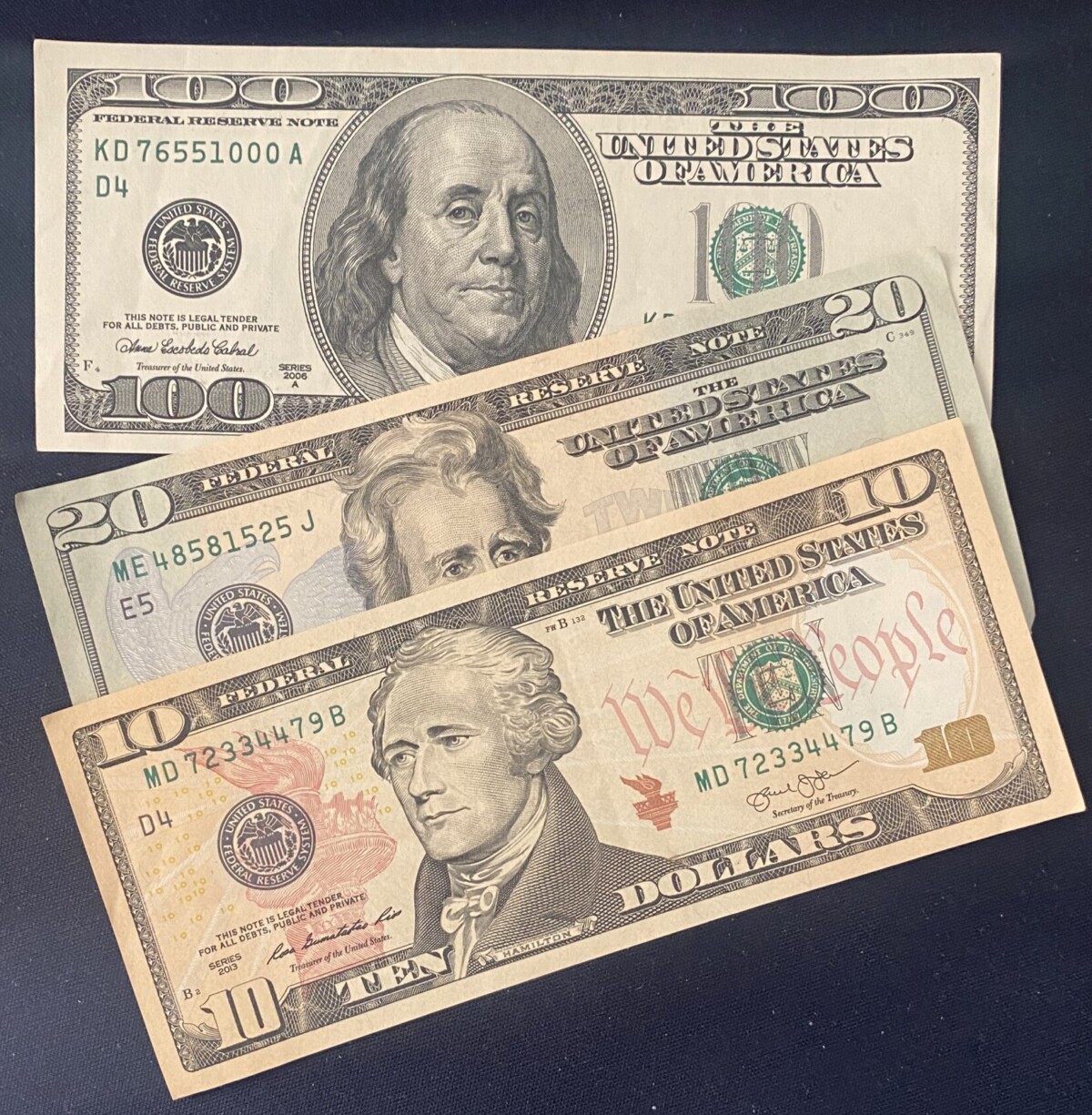
ドル160円台の経済、39年前の日本人は「こんな結末とは・・」と嘆き、悲しむ
円安が進んでいます。1ドル160円台は1986年12月以来。2024年6月末時点で37年と6ヶ月ぶりです。記録の数字を見る限り、なんか凄そうな円安ドル高に思えますが、正直いって「当然かな」という気分です。
この30年間余り、経済成長も年収も横ばい、事実上ゼロの数字が並んでいるにもかかわらず、日本は腹を括った改革や挑戦を先送りし続けました。現在の円安の背景には日米金利差などがあると訳知り顔で説明する向きもありますが、単に日本経済の実力を表しているだけです。
37年前、いや39年前の1985年9月のプラザ合意の時、真っ青な顔をしながら企業戦略の舵取りを切った経営者を目撃しているだけに、30年以上の年月を無駄に費やしてしまった寂しさが募ります。あの時の経営者、従業員らみんな同じ思いを抱くでしょう。「こんな悲惨な結末が待ち構えていたとは、想像もできなかった」。
円高へ転じたプラザ合意から39年
日本円がドル高へ大きく転じた1985年9月のプラザ合意。日本経済の基幹産業である自動車業界を取材する新聞記者でした。プラザ合意が明らかになった9月22日はちょうど欧州での取材を終えて飛行機に乗って日本へ向かっている最中。ドイツ・フランクフルト空港で手元に残っていたドル紙幣は1ドル242円程度でしたが、成田空港に到着したら220円程度に。
驚いている間もなく自動車業界の取材に向かうと、どんどん円高が加速します。プラザ合意に至る引き金のひとつは日米間で過熱した自動車輸出摩擦です。円高によって打撃を受ける標的でしたが、当初は自動車メーカー経営者に余裕が見えました。「円高は経営に打撃ですよ」と話しますが、口元は笑います。半年足らずで1ドル180円台が見えてきたら、もう表情は真っ青。「日本経済の正念場はここから始まる」。肝に銘じ、その現場を目撃できる幸運に感謝しました。
経営者は日本を捨てる覚悟を
円高は止まりません。プラザ合意から1年5カ月後の1987年2月には1ドル155円、年末には130円までぶっ飛びます。翌年1月には120円台に。その後は120円台から140円台までの水準が続きます。自動車メーカーは日米貿易摩擦の解消と急激な為替変動を乗り切るため、米国での現地生産を拡大。これに伴い自動車部品を供給するトヨタ自動車や日産自動車などの系列企業も米国へ進出します。「日本の産業の空洞化」を懸念する声が広がりますが、日本を捨てなければ生きていけない瀬戸際に立っていたのも事実でした。
ところが日本国内は一変します。円高不況を食い止めるため、政府・日銀は日本円をジャブジャブと増やします。お金が溢れ、その受け皿として不動産、高級ブランド品が高騰。バブル経済が知らぬ間に沸騰し、数字の上では好景気が到来しました。プラザ合意で日本経済は窮地に追い込まれたはずだったのに、いつの間にか株価や不動産価値の急騰で「ジャパンマネーで米国全ての土地を買収できる」という奇妙な優越感に酔い、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を真実と勘違いしていました。
バブル経済に酔い、日本の未来を勘違い
「日本経済は正念場」という決意はどこか遠くへ散り散りになって消え去り、挑戦と改革を忘れた日本経済、企業経営に安住する時代が始まりました。自動車は円高を乗り切った自信を踏み台に世界市場を席巻し、トヨタは世界一の座にまで上り詰めます。しかし、自動車と並ぶ強さを見せたエレクトロニクス産業は、半導体、テレビ、オーディオなどで次々と韓国、台湾勢に追い越され、今ではあのパナソニックでさえ「その他大勢の家電メーカー」の列に並びます。
円高は1995年4月に79円75銭と80円を切る水準に高騰しました。偶然にも当時、シドニー支局に駐在していましたので、80円割れの第1報を発信する幸運?にも恵まれたしたが、すでに日本経済の屋台骨の骨密度が低下しているのですから、1990年代半ばからの円高でもう足元はふらついています。
人件費抑制など目先の収益にこだわる
日本の企業は人件費を抑えるため、非正規雇用を増やしますが、人材力も同時に低下させます。目先の利益にこだわる経営戦略は、企業の挑戦、言い換えれば思い切った投資意欲を奪います。中長期の経営戦略で企業体質の変革、新規事業への進出を謳いますが、内実はここ数年の利益をどう確保するかに汲々としていました。2011年3月の東日本大震災などをきっかけに円高は進み、10月に75円32銭と過去最高値を記録しましたが、日本経済に円高に立ち向かう気力は残っていませんでした。株価は底を這い、決算数字は取り繕っているのが傍目でわかるほど。
2013年3月、潮目は変わります。黒田東彦日銀総裁が誕生し、大規模な金融緩和などで円安へ誘導。輸出企業の収益回復など日本経済へのプラス面が強調されましたが、企業に飛躍する筋肉がわずかしか残っていないのですから、1980年代のような日本企業の強さはとても望めませんでした。
30年間で憔悴し、挑戦力は萎える
しかし、円安はお構いなく進みます。日本は金利ゼロなど金融緩和を続ける一方、米国はインフレ抑制に向け金利を引き上げる。日米の金利差が広がれば、当然ながら円安は加速します。黒田総裁から植田総裁へ変わり、金融政策の軌道修正を掲げられますが、この30年間で憔悴した日本経済の体力に変わりはありません。
1980年代、円高急騰に真っ向勝負した気力が企業経営者に残っているのでしょうか。1980年代、ドル円の為替相場とともに企業経営の舵は大きく変わりましたが、2024年の円安はドル円相場だけが一人歩きしている印象です。小さい頃、過去と未来を行き来する米国のテレビ番組「タイムトラベル」に熱中しました。もしタイムトラベルを使って1980年代の経営者が2024年の日本経済を目にしたら・・・。寂しい表情が目に浮かびます。