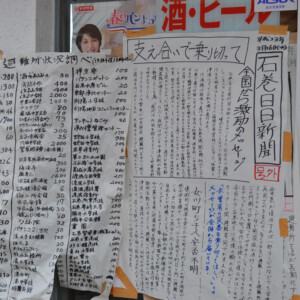実録・産業史9 )スバルはこだわり技術集団か凡庸な経営か
「私の産業史」自動車編は時代背景や登場人物をわかりやすく説明したいと考えて仮名を使いながら、1980年代から繰り返された自動車メーカーの浮沈を再現してみました。連載はまだまだ道半ばですが今回で9回目に入ることもあり、今回は趣向を変えて「実録・産業史自動車編」に切り替えて「100年に一度」といわれる世界経済の変革期に直面する自動車メーカーを描写してみます。シリーズ連載の「味変(あじへん)」みたいなものです。
世界の自動車産業は内燃機関のエンジンを捨て電気モーターで走るモビリティに転進しようとしています。その先の未来は空飛ぶ移動体へ飛躍するのでしょうか。まだ視界不良の未来に向けた解を見つける主役は誰でしょう。やはり会社経営の最高責任者である社長・CEOがその重責にを担うか。思いも掛けない新しい経営の主役が登場するのかもしれません。自動車メーカーの過去、現在をもう一度振り返りながら考えてみたいです。
企業が存続する力とは何か
日本の自動車メーカーで他を圧倒する経営力を感じさせないにもかかわらず、生き残るだろうと確信するのがSUBARUです。戦前の中島航空機を前身に独創的な技術を継承し進化させながら、世界の自動車メーカーの中で存在感を示しています。水平対向エンジンと4WD(四輪駆動)を企業のアイデンティティに根強いファン層を囲い込んでいます。エンジンやシャーシーなど基本性能に力は入りすぎていたせいか、車体のデザインは優しい表現で言えばとても個性的、辛口で言えば褒めるところが少ないキャラクターを見せつけてくれました。エンジンやシャシーの性能ではポルシェやアウディとそんなに遜色ないと思いますが、デザイン力の差はなんともしがたいものでした。野暮ったいとはSUBARUのためにある言葉かも、です。ただ、最近は格好良いですよ。野暮ったさが消えて洗練されてきたのが逆に寂しいです。
無骨な技術集団も見逃せない
しかし、無骨なクルマ作りがSUBARUの強さを生む源泉でした。歴代経営者の力量の現れと評したいところですが、戦後の混乱期である創業直後の苦闘は経営者、従業員のみなさんの努力と汗の結果で乗り切ったわけですし、1968年からの日産自動車との資本提携以降は社長は日産自動車と日本興業銀行から派遣された方ばかりで、歴代の皆さんを熟知しているわけではありませんが全員が当時の富士重工業のためと考えていたかどうかは残念ながらわかりません。幸いにも4代目社長の大原栄一さん以降の皆さんとは取材でお世話になりました。6代目にあたる興銀出身の田島敏弘さんは話題を集める、いわばニュースの見出しになる社長でした。興銀調査部長として名を馳せた方ですから、将来予測が大好き。頭の体操のような新車開発、経営戦略を発表し、将来の夢を膨らませます。後継の7代目、川合勇さんは出身母体の日産自動車社長になるのかもと思われた人材です。人間的にも重量感がありました。歴代の社長は当然のことながら会社の未来を考えて経営戦略を実行しています。
しかし、SUBARUが生き長らえた最大の理由は技術にこだわり続けた開発部門の意地です。販売店は今でも「トヨタならこのディラーはコテンパンに叱られる」と思うレベルです。にもかかわらずSUBARUの車はヒットします。最近の半導体不足に伴う販売台数の低下についても「受注は順調で売れない心配はないです。納車がかなり遅れてお客様にご迷惑をかけるのが申し訳ない」と話す販売店の営業担当者の表情に不安の色は見えません。
クルマが勝手に売れているのです。クルマの強さを生み出す意地を体現したのが「アルシオーネ」です。SUBARU、当時富士重工業の開発陣が胸いっぱい膨らました夢が注入されていました。1985年に発表されたアルシオーネは、中島飛行機の伝統を受け継いでエンジンは水平対抗6気筒を搭載し、自動変速機(AT)やシャシーなど駆動系には最新のアイデアを容赦無く盛り込みました。車体デザインは飛行機をイメージする尖形の奇抜なものです。戦闘機のキャノピーを模したそうです。開発主査を取材し記事も書きましたが、思いの丈を存分に話してくれました。
でも、アルシオーネは売れません。理想を追求した開発陣の独りよがりと言われても仕方がないのですが永遠の名車です。自分たちが磨き上げた独創的技術へのこだわりが中小メーカーでありながら、米国や豪州などで走行性能に対する信頼性を獲得し、トヨタでも日産でもホンダでも得られないブランドの地位を獲得した理由でした。
自動車はモノです。手で固まりを感じることができます。ブランドは空疎です。きっと手の感触で確かめることはできません。しかし、価値は無限大です。19世紀に自動車が誕生して以来、固まりとしての価値と無感触のブランドとしての価値が均衡しながら、世界の自動車メーカーは企業価値を高めてきました。
だからこそ自動車メーカー歴史には創業者の熱い哲学を見ることができます。今でも創業家が経営を継承する自動車メーカーが主流です。世界最大の自動車メーカーの地位に就いたトヨタ自動車、フェルディナンド・ポルシェに遡ればフォルクスワーゲン (VW)もポルシェも親戚です。フォード、事実上の創業者である鈴木修が率いるスズキ、マツダなどが続きます。
電気自動車(EV)の時代を迎えた今なら、イーロン・マスクのテスラですか。電気自動車がこれだけ普及する勢いを後押ししたのはイーロン・マスクの狂気に近いEV時代到来に対する確信です。それは軽自動車を日本の車の3分の一にまで普及した鈴木修にも通じます。
創業家の自動車メーカーは浮沈の歴史
栄光の歴史は浮沈の繰り返しの歴史を招きます。ヘンリー・フォードが導入した大量生産のモデルで世界有数の地位を築いたフォードは創業家の好き嫌いで経営者選びが行われ、どん底寸前にまで追い込まれます。日本でも創業家の松田耕平が夢見たロータリーエンジンの実現にかけていまだにその呪縛が逃れていないマツダがいます。
生き残りに経営哲学が必要か
SUBARUには経営者の哲学はありません。組織というか茫洋とした求心力の哲学があるだけです。自分たちが継承した技術を守ることです。面白いですよね。創業者哲学を引き継ぎながら会社の軸を探し続けるホンダがある一方で、その時その時の優秀な創業家出身、非創業家の社長を輩出しながら時代を乗り切ってきたトヨタ自動車は今、凡庸な社長が現れて「100年に1度の革新」と言いながら水素エンジンぐらいしか唱えられない。
創業家の自動車メーカーだからといって未来が保証されているわけではありません。創業家の自動車メーカーが存続できているのは、自動車産業の新規参入の壁がそれだけ高い証拠です。だから中国の自動車産業を見てもわかるように国の後押しが欠かせませんし、イーロン・マスクのテスラにしても自身に巨額資金があるからこそ電気自動車の開発と工場建設を継続できたのです。単純に言えば統計学でいう大数の法則が証明されているようなものです。
技術にこだわる求心力で生きるスバルは、凡庸な創業家の社長が率いるトヨタと組んでEVを近く発表します。資本提携の関係が有るとはいえ、これまでのように付かず離れずのまま行けるのか、それとも取り込まれるのか。良い意味で空気を読まないSUBARUの経営が変わるかどうか。自動車メーカーの底力を測る試金石と考えています。それはこれから20年間、生き残る自動車メーカーを見極める見晴台の一つだと思っています。
「今回だけ実録・産業史」は次回も続け、ようやくですが「will be in the melting pot」の溶け具合を考えてみるつもりです。