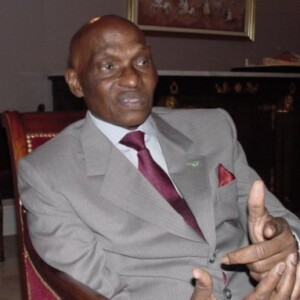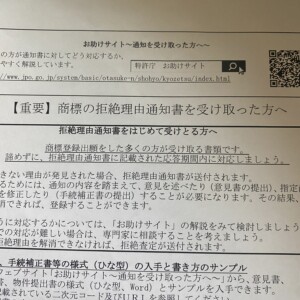地中美術館は「注文の多い料理店 」アートをおいしく楽しめず「注意」に従うだけ
香川県直島の地中美術館を初めて訪ねました。本州の中国地方と四国に囲まれた瀬戸内海の沿岸には素晴らしい所蔵品を展示する美術館が多く、国内外からアートを楽しむ観光客が集まってきますが、地中美術館は人気美術館の一つじゃないでしょうか。
草間彌生のカボチャがお出迎え
直島には岡山県玉野市の宇野港、あるいは香川県高松市などからフェリーなどで到着します。港で出迎えてくれるのは草間彌生さんの赤いカボチャ。異空間の扉を開くワクワク感を期待させるインパクトを放っていたのは流石でした。

地中美術館のコンセプトはもっと異彩を放っています。ベネッセ創業者の福武總一郎さんがクロード・モネの「睡蓮」を購入したのをきっかけに建設され、世界的な建築家として名を馳せている安藤忠雄さんが設計しました。直島南部の山にあった塩田跡地を利用しており、入り口やカフェなど一部を除き地中に埋まっています。安藤さんが尊敬する仏建築家ル・コルビジェをオマージュするかのように打ちっぱなしのコンクリートが建物を個性を醸し出しています。
展示はモネなど3点だけ
展示する作品はわずか3点。クロード・モネの「睡蓮」のほかに、階段状の空間と花崗岩の球を素材にしたウォルター・デ・マリア、遠近感を失う青い光に満たされる空間を演出したジェームズ・タレルを加えています。
モネの睡蓮をテーマにした作品はこれまでも数多く見ていますが、地中美術館のモネはニューヨーク近代美術館のように大きな空間にゆったりと展示されています。入館は時間指定予約ですから、ゆっくり鑑賞できるよう配慮してくれています。どんなモネが待っているのか。当然、期待しちゃいます。
港からバスを乗り継ぎ、美術館の玄関に到着。バスを降りると、猫が「ミャア〜」と迎えてくれました。とても人に慣れており、まるでひとりひとりに「よく訪ねてきましたね」と声がけてしているようでした。待合でしばらく時間を過ごして入館時間、午前10時を迎えました。
美術館のエントランスを抜け、モネが展示されている空間に向かいます。館内は予想よりも暗く、打ちっ放しのコンクリートの壁面が空間を遮る圧力となって存在感を示しています。安藤忠雄さんが居るかのような威圧感を覚えるほど。下り坂の通路に入ると、中庭がありました。緑色の棒に見える植物が一面に植えられていました。コンクリートの冷たさと生きる力を対比しているのかもしれませんが、畑で野菜を育ててきた自分には響いてきません。
注意事項は多数
モネの展示室に到着したと思ったら、周囲の明るさが失せていきます。係の人が立っており、「靴を脱いで、スリッパに履き替えてください」。あたりが暗いので「えっ、どこで」と思い、見回すと2段重ねのベンチのような棚があります。入館者はそれなりの人数が固まりとなって移動しているので、靴とスリッパを履き替える空間と時間が必要ですが、周囲が暗いのでちょっと危ない。
「棚に座って履き替えても良いんです」と係の人は話しますが、その棚との距離感が危ういのです。館内を暗くする何かの意図はあるのでしょうが、せめて履き替える場所ぐらいはスポットライトで足元がよく見えるやさしさが欲しい。美術館の雰囲気を変えることはないでしょう。「ニューヨーク近代美術館のモネの部屋は靴のまま入ったのに、日本は靴を脱ぐのか」とボヤいていたら、係の人が注意事項を話し続けていました。全然、耳に残りません。
「まるで注文の多い料理店ですね」と宮沢賢治の寓話に喩えて話しかけたら、係の人は耳にイヤホンは入っているので伝わりません。イヤホンを外して「何か」と聞かれましたが、2度も「注文の多い料理店ですね」と話す気はしません。それよりも、入館者の問いかけが伝わらない展示室の案内係に疑問が湧いてしまいました。あとで気づきましたが、館内の案内係はイヤホンをつけており、話しかけてもすぐには応答できないようです。
入館者と地中美術館のコミュニケーションの断絶。この事実が地中美術館を語るキーワードかもしれません。モネの展示室でも他の入館者が「睡蓮」のそばで立っている係の人に質問しても、ほとんど会話になりません。モネの傑作は沈黙して鑑賞するのがマナーなのです。絵画はガラスで覆われています。傷つけられる恐れはありますが、やはり「生」で見たいです。モネの睡蓮がまるで「ダメ、ダメ」の2文字に見えてしまい、感情移入ができません。
ジェームズ・タレルの展示室はもっとコミュニケーション不足でした。青い色に包まれた幻想的な空間が目の前にあります。空間ですが、一つの塊のようです。「私がそこまでと言うところまで進んでください」と案内係は注意を促しますが、初めて入った室内の距離感がわからず、立ちすくみます。どこまで進んで良いのかわかりません。
目の前が平坦なのか、上っているのか、下っているのか。その戸惑いも作者の意図の一つかもしれませんが、入館者が戸惑い続けていたら、係の人はなにかのアドバイスがあっても良いでしょう。恐る恐る幻想的な空間を歩み進むと、青い色の濃淡に変化が生まれ、プリズムの中に入り込むドキドキ感が生まれましたが、作者の意図は感動よりも歩み進む戸惑いなのか。ふと考えてしまいました。
ウォルター・デ・マリアの展示室は注意事項がもっと増えます。「室内は響きますので、静かに歩いてください。金色の部分は触ると禿げますから、触らないでください。・・・・」と立板に水のように続きます。いっぺんに覚えられません。白くて大きな室内空間は、神殿のようでした。白い階段が続く途中の台に花崗岩の球がドンと鎮座。展示室を囲む白い壁際に金色の短い柱が短冊のように至る所に立っています。
歩くと確かに響きます。神殿は崇高さを誇示するために音響が良くなるように設計されていることを思い出しました。他に入館者がいないことを確認して室内の係の人に「誰もいないので、パンと手を叩いて良いですか」と訊ねたら、OKと笑ってくれたので軽く手を叩きました。案の定、とても良い反響が生まれました。
作者の意図は不明ですが、室内に配置する金色木製の短冊は遠めにはコンサートホールの反響材に見えます。作品そのものにもともと反響効果を組み込んでいるのではないでしょうか。花崗岩の球上部には天井の窓が映り、全体を見渡すと仏様か神様が球に鎮座して見えます。室内で待機していた係の人に訊ねたら「青空の時は、黒色の球上部に青空が窓枠のまま映り、白色の壁面、金色の短冊で構成する絶妙な景色になります」と教えてくれました。その瞬間、神殿になるのでしょう。
宮沢賢治の寓話の挿絵が頭の中に
にもかかわらず、入室時に「静かに室内を移動してくだい」と注意するとは?せっかくの作品の独創性を鑑賞できないのでは?と不思議です。
地中美術館を出た後、奇妙な気分になりました。作品を鑑賞に訪れたのか、あるいは作品を見せてもらったのか。「こんなすごいものがあるんだよ」と美術館に自慢されているようでした。
美術館は展示方法や作品などを介して入館者と会話し、楽しむ空間だと思っています。それは勘違いでした。地中美術館は、お客が高級フランス料理のマナーを厳密に守るかどうかを注視し、「これが高級料理だよ」と教えてくれる「注文の多い料理店」でした。帰りの道を歩いている最中、宮沢賢治の寓話の挿絵が頭の中を駆け巡り、「料理されているのは実はあなたなのだ」と諭されている気分になってしまったのが残念です。