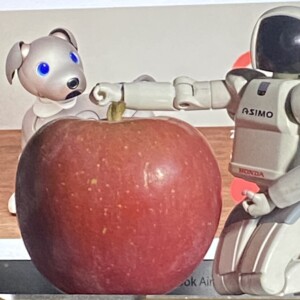日産は追浜と共に消えるのか トランプ関税に大騒ぎするぐらいなら、政府が日産を救済したら
「日産」の文字がどんどんセピア色に染まっていきます。もう歴史に埋もれる自動車メーカーになる日が近づいているのでしょうか。寂しいですね。
日産がセピア色に染まる
日産自動車が追浜工場(神奈川県横須賀市)を閉鎖する方向です。1960年代から操業を開始し、歴史のある古い工場ですが、日産の主力工場の中でも最大の車両生産能力を持ちます。神奈川県を創業の地とする日産にとって「オッパマ」という呼び名は格別の響きを放ちます。
なにしろ、最先端の工場として「技術の日産」を担う先陣を切っていました。複数の車種を同じ生産ラインで組み立てる「混流生産」を真っ先に導入したほか、1970年代に日本で初めて溶接ロボットで車体を成型し、生産ラインの自動化に先鞭をつけます。
生産車種も日産の主力車ばかり。ブルーバードはじめプリメーラなど中小型車の生産拠点としての地位を誇ってきました。現在も日産が世界に先駆けて量産した電気自動車(EV)「リーフ」、日産で最もヒットしている「ノート」を生産しています。
追浜工場が構える神奈川県は日産の牙城。今は見る影もないですが、1990年代までは日産系列の主要部品メーカーの工場が神奈川県内に集積していました。厚木市には新車開発など技術部門の最大拠点のテクニカルセンターがあります。新車開発に向けた新技術、部品の調達、完成車に組み立てる生産技術などクルマに必要なノウハウが神奈川県内のあちこちに蓄積されていました。そんな大袈裟なと笑うかもしれませんが、追浜工場は今や落城寸前と言われる日産の中で唯一、残る天守閣のようなものでした。
「オッパマ」は別格
日産は1990年代から経営不振を打開するため、工場閉鎖が続いています。独VWの「サンタナ」をノックダウンするなど自動化工場のモデルともなった神奈川県の座間工場を閉鎖したほか、2000年以降もルノー傘下に入り、カルロス・ゴーンの指揮で進めた経営再建策「リバイバル・プラン」で村山工場などが閉鎖されました
それでも生産能力の過剰感を解消できません。カルロス・ゴーンは一度スリムになっても過大な販売目標に向かって突っ走り、それが裏目に出て北米などで多額の販売奨励金を浪費して経営内容は再び悪化。自業自得と笑うわけにはいきません。ゴーン追放後を継いだ西川廣人、内田誠の両社長はゴーンが残した病巣に効く処方箋を考える能力も努力もありませんでした。
2025年3月期に6000億円を超える過去最大級の赤字は、悲しいかな必然の結果です。2025年4月に就任したイバン・エスピノーサ社長からみれば、誰もがもっと早めに手立てを打てばと考えたリストラ策を実行するしかありません。それが追浜工場も含む日産車体の湘南工場(神奈川県平塚市)、海外ではメキシコなど4カ国で5工場を閉鎖です。
ただ、追浜工場閉鎖のインパクトは計り知れません。日産全体の工場の操業度は4割程度だったといわれていますから、採算分岐点を大幅に割り込んでいるのは事実です。余剰生産能力があるとはいえ、追浜工場で生産している数少ないヒット車「ノート」を存続する栃木工場、九州工場(福岡県苅田町)ですぐに引き継ぐことができるのでしょうか。
下衆の勘繰りと笑われると思いますが、追浜工場を閉鎖対象にしたのは、売却後の不動産価値が最も高いから選んだとしか思えません。座間や村山の跡地はショッピングモールに変わりました。閉鎖後の混乱は後回しになったのではないかと勘違いしそうです。
INJCに志賀さんがいるじゃない
もう一つ寂しいことがあります。石破首相ら政府の声が聞こえてこないことです。日産は民間企業ですから、存続すかどうかは自己責任。政府が深く関わり、前面に立って救済することはありません。しかし、トランプ関税であんなに自動車産業の悪影響について日米で大騒ぎしているぐらいなら、日産の経営建て直しにもう少し関与してもおかしくないでしょう。神奈川県の地域経済はもちろん、次世代モビリティのEV開発などで日産の力はまだまだ必要です。
そういえば官民ファンドの産業革新機構を継承するINJC会長には志賀俊之さんがいます。カルロス・ゴーンが率いた当時の日産ナンバー2として知られています。政府主導の政策に日産出身者を活用しているのですから、半導体の復興に何兆円も費やす経済安全保障の延長線上に、中国、欧米と競うEVの未来に1兆円使う新たな政策を立案したらどうでしょうか。