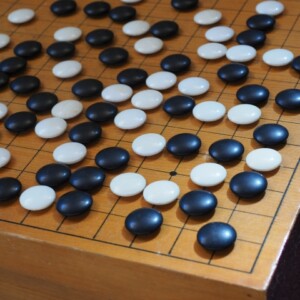米国セブンイレブン ベタベタの床に商品が並び、デビットは不発 警備員が店内を睨む
ニューヨーク・タイムズが9月9日付記事でコンビニ「セブンイレブン」を取り上げ、「アメリカは日本式セブンを受け入れる準備があるのか」と問うています。セブン&アイのスティーブン・デュカス社長のインタビューを交え、日本のセブンイレブンが定時配送する物流システムを使い、新鮮でおいしい惣菜品を提供するコンビニモデルを米国でも採用し、米国のセブンイレブンを一新する戦略を説明していました。
NYT紙は日本のエッグサンドウイッチを高く評価
記事の前提には米国セブンイレブンの不振があります。同紙の過去のセブンイレブン関連の記事を読むと、日本のセブンイレブン経営を概ね高く評価しているようです。例えば日本を訪れる外国人観光客でも高い人気を集める「エッグサンドウイッチ」を例に優れた商品開発力、それを支える物流、食材調達力に注目しており、日本で成功しているビジネスモデルを米国で実現できるのかと問題提起していました。
日本のセブンイレブンに慣れ切った消費者としては、ちょっと驚きです。「ファミリーマート」「ローソン」のライバルに店舗売り上げで差をつけられ、かつての輝きを失ったセブンイレブンにがっかりしていたからです。ニューヨーク・タイムズの視点は日本のセブンイレブンを過大評価しているのでは?と思ったほどです。
もっとも、セブン&アイはコンビニ事業で失敗することはできません。イトーヨーカ堂などスーパー事業を売却して、コンビニ事業に注力して復活を遂げる再建策を進めています。成功のカギは日本のみならず北米のセブンイレブン再建が必須条件です。せっかくカナダのコンビニ大手が繰り出した買収提案を跳ね返したばかり。ここからの踏ん張りが大事です。
米国のセブンイレブンは想像を超える
しかし、米国セブンイレブンの現状は想像以上というか、想像以下でした。
1年前、ニューヨークの人気エリア、タイムズスクエア周辺のセブンイレブンを回りましたが、日中はガラガラ。周りのピザやお弁当屋さんはお客さんが並んでいただけに、その差にびっくり。ただ、セブンイレブンは全米で1万店を超えるチェーン展開しているわけですから、わずか数店で実情がわかるはずもありません。
というわけでもありませんが1年後、ニューヨークに次いで全米第2位の大都市、ロサンゼルスのセブンイレブンに通ってみました。ニューヨーク、ロサンゼルスの店舗運営が中途半端なら、北米のコンビニ事業が上昇気流に回復できるとは思えませんからね。
ロサンゼルスでは、都心のダウンタウンや郊外の店舗を訪れました。郊外の店舗は周辺エリアの住民の所得層が高いこともあって、なんか日本のセブンイレブンって感じでした。ちょっとホッとしました。
ところが、ダウンタウンの店舗は空気感が全然、違いました。同じ都市圏なのに、同じセブンイレブンじゃない?って感じでした。
訪れた時間は午後8時ごろ。市役所や主要駅がある都心のダウンタウンとはいえ、日中とは打って変わって街を歩く人は少ないですし、治安の良くない街区があります。翌日の朝食用にサンドイッチやオレンジジュースを買いに入った店舗はビル1階にあり、交差点に面した立地です。外からガラス越しの店内は丸見え。歩道や車道も照らす明るい光を放っていました。安心感はあります。
夜8時過ぎのロサンゼルスの店舗は
でも、入り口がわかりにくい。ドアは何面かあるのですが、誰も彼もがすぐに店舗に入れないように制限しており、1カ所に絞っているようです。入り口のガラスドアを開け、店舗を入った印象は正直、雑然の一語に尽きます。初めて入った店舗なのでどこに商品があるのかわからないこともあるので、雑然という印象は失礼ですが、色鮮やかなビニール袋に包まれた商品が並ぶ日本と違って白黒に近い空気感です。
店内を歩くと、履いているスニーカーがペタペタと音をたてます。洗剤で消毒したせいか、原因はわかりませんが、靴底がワックスの油に吸い付きます。オレンジジュースなど冷やした飲料を収納した冷蔵ケースが店内の一番奥に向かって歩くと、靴底からペタペタ、時々ベタベタの感触が続きます。カゴにオレンジジュースを入れ、今度はサンドイッチの棚を探し始めたら、店の中央部あたりの床にミネラルウォーターのボトルの山があり、その横のスチール棚にビニール袋に入ったパンも積み上がっています。これから調理するのか、それとも陳列するのかわかりませんが、仕入れ業者が納入した後に一時的に置いている印象でした。
サンドイッチなど調理パンは午後8時過ぎということもあって、品数は多くありません。ハムやサラミを挟んだホットドック風のサンドを買いました。
レジには担当スタッフが1人いましたが、お客なのか友人なのかわかりませんが、雑談中。待つしかありません。こちらに気づき、買う商品の支払いを計算してデビットカードで決済しようとしたら、不通。他のお店では決済できたデビットカードでしたが、何度試みても決済できません。「おかしいなあ。電子決済システムに支障があるのじゃないの?」と心の中で思いながら、他のクレジットカードで試したらOK。
翌日、「持参したデビットカードが使えなくなったのかもしれない」との不安なこともあって、街中の屋台村のようなマーケットで夕食時に利用したら、問題なく決済できました。「やっぱり問題ない」と確信してその足で昨夜と同じセブンイレブンを訪れ、買い物した後に使ったら、やっぱりダメ。セブンイレブンはデビットカードを使えないのかと勘違いしそうになりました。
日本のセブンイレブンとは程遠い空気
その夜も昨夜と同じようにグループのお客が店内でたむろしています。グループとは別の1人の少年が現金を握りしめて、買いたい商品をレジの前に並べ支払い金額を計算をしていました。レジの担当者は、一緒にチェックして「これはダメだな」と言い、除いたりしています。
米国はキャッシュレ社会ですから、現金で買い物する風景はそう見かけません。複雑な心境で眺めていたら、出入り口のそばに立つ警備員が店内を見渡していました。胸を張って「自分がちゃんと監視している」と体から訴えていました。
日本のセブンイレブンとは程遠い空気を味わいました。「エッグサンドウイッチを食べたいから、セブンイレブンへ行こう」という気分にはなりません。だからこそ、ニューヨーク・タイムズの記者は「日本のセブンイレブンを米国へ移植してほしい」と思ったのかもしれません。しかし、その道のりはとても遠い。同紙の記事が夢物語のように見えてきます。
◆ 写真はニューヨークのセブンイレブンです。