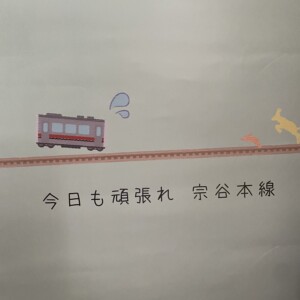日本は世界に誇る1000年企業はあるが、なぜ世界的なベンチャーを輩出しないのか
日本経済の強さの根源は製造業にあります。石油やガスなどエネルギー資源が乏しく、四方が海に囲まれる大陸から離れた島国であるにもかかわらず、経済大国に発展できたのは世界が評価するものづくりの技術があるからです。
金剛組は1500年近い
その象徴は金剛組でしょうか。創業は578年。聖徳太子が朝鮮半島の百済から宮大工を呼び、現在の大阪市に天王寺を創建しますが、宮大工の1人、金剛重光が創業しました。以来、1500年近い歳月が過ぎ、世界最古の企業です。当時の工法は今でも「組み上げ方式」として継承されており、日本の精緻な加工と設計など「ものを創る」技術がいかに素晴らしいのかがわかります。
日本には創業が1000年を超える企業が11社もあるそうです。創業100年ならば4万5000社にも。世界的なビジネススクール、米ハーバード大学経営大学院でも日本の「長寿企業」の経営に高い関心が集まっています。
米国はシリコンバレーなどから世界を制するユニコーン企業を輩出しており、そのオリジナリティとバイタリティがとても羨ましいのですが、「隣の芝生は青い」の例え通り、なぜ日本に1000年を超える企業があるのか研究したくなるのでしょう。
ハーバードなどが研究
背景には米国もファミリービジネスが多い。世界最大のスーパー、ウオールマートはじめ有力企業の多くは今も創業家が大株主として力を保持しています。株式上場せずに米国の政治経済を握る知られざる巨大ファミリービジネスも多く、大統領選の資金貢献などで時々顔を出します。かくいう、トランプ大統領の不動産を軸にした事業は政治と経済が一体化したファミリービジネスそのものです。1000年はともかく100年以上も事業と経営を継承し続ける理由を探るには、日本の長寿企業を解析するしかないでしょう。
裏返せば、なぜ日本は1000年を超える企業が存続できたのか。経営環境が大きく変化したとしても、創業家を求心力に技術力を継承する組織運営が奏功したのだと思います。和菓子の虎屋は典型例です。室町時代から京都の御所に納めていましたが、東京遷都の時に老舗の多くが京都に残る中、東京へ移りました。様々な中傷が飛び交ったそうですが、創業家の黒川家を軸に500年続く虎屋の味を守っています。
創業家を掲げ、技術を伝承する。日本の企業の強みである半面、次代を担う技術の創造力を鈍らせているのも事実です。優れた技術を守ることを最優先してしまうと、新しい技術革新に挑む機会が減ってしまいます。買い手のニーズに合わせられなければ事業は当然、行き詰ります。
1000年企業の代表である金剛組は、神社仏閣が木造からコンクリートへ移り始めた結果、事業が行き詰まり、2005年に中堅ゼネコンの高松建設に救済され、子会社となりました。
技術の継承は時代の破壊を抑止
日本から世界をリードするベンチャー企業が輩出しない理由の一つです。常識に捉われない破天荒なアイデアと事業創出に挑む人材を育てる土壌が少ないのです。社会を変えるイノベーションは「若者、馬鹿者、よそ者」から生まれると例えられますが、技術の保全を重視する風土では若者は修行不足と叱られ、馬鹿者、よそ者は何も知らないビッグマウスと笑われるだけです。
好き嫌いはあるでしょうが、イーロン・マスクのような時代の破壊者、ディスラプターを許す社会ではありません。トヨタ自動車をみてください。創業家の豊田章男会長は電気自動車(EV)など新エネルギーへの進出を表明しながらも、エンジン車への郷愁を語り続けます。自動車産業を支配するトヨタが自社の枠内で進めるEV戦略が世界をリードできるのでしょうか。
1000年企業は日本が胸を張って誇れる最強の存在です。ただ、「最強」を死蔵してしまっているのも日本の現実です。ハーバードビジネススクールなどが「日本発のユニコーン企業」を研究する日がいつ訪れるのか。悩ましい日々が続きそうです。