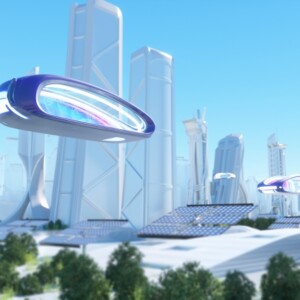ほぼ実録・産業史 自動車編 will be in the melting pot ⑦ ルソー救済劇の前奏曲、日進自動車の凋落が始まる
日進自動車とルソー自動車の提携。1999年に世界第4位の自動車メーカーグループが誕生した。規模は大きいが、内情は経営危機に陥った日本とフランス大手同士が手を結んだ弱者連合に過ぎない。フランス政府とルソー自動車による日進の救済劇と思われがちだが、端緒のルソー自動車身売り話から追っていた私はフランス政府によるルノー救済がその実相であると考えている。両社とも理想の相手とは話が進まず、目の前に残っていた相手と目と目が合ってしまった。結末を決めずに、いや決められないまま始まったドタバタ劇は舞台に迷い込んだ日本の元人気俳優を捕まえて、強引に幕を閉じた。「さすがフランス、思わぬ結末だ」と感心していたら、名経営者と持ち上げられていた人間が突然解任され、当の本人は箱に隠れて国外逃亡する犯罪事件まで巻き起こす番外編が待っていたのには驚いた。
世界の自動車産業は1990年代に入って再び提携・合併が動き始めた。日進とルソーの提携は自動車再編劇の一幕に過ぎないが、日米欧の主力メーカーが次々と舞台に登場するため、自動車産業史として特筆に値するだろう。結末が決まらないまま始まった劇と書いたが、舞台上の登場人物、セリフはまるで即興劇そのもの。ピンボールゲームを見ているように毎回予想外の動きが待っている。右に飛んだかと思えば左上に振れ、運が悪ければ最下部の奈落に吸い込まれてしまう。自動車メーカーは国を支える基幹産業であり、国を代表する企業ともてはやされるが、転がり始めたら誰も止められないのだ。
その前奏曲は日進自動車の変調から始まった。「Aー1」「ジーマ」などバブル経済の象徴ともなったヒット車を相次いで飛ばした日進の勢いは加速しているかのように見えた。しかし、1990年代のバブル経済が忽然と消えた時、底が抜けたように足下の利益が消えていった。日本経済のバブルが弾けた1992年3月期では赤字決算に転落した後99年3月期までの7年間、98年3月期を除き赤字決算が続いた。有利子負債は3兆円に迫った95年3月期をピークに2兆円台が続く苦境に追い込まれた。
なぜ日進自動車は1990年代に崩壊し始めたのか。新車開発は確かに永遠のライバルである織田自動車を上回っていた。1980年代に「90年代に技術世界一をめざす」、別名「901活動」は欧州車に劣るとされたシャーシやサスペンションの足回り、操縦安定性の飛躍的な向上に成功し、スポーツカーで圧倒的な人気を集める一方、主力セダンでも高い評価を集めた。個人的にも取材を通じて惚れ込んだ新車開発の主査が担当した「プリメーラ」を買い、走っても走っても楽しいセダンがあることを知った。織田自動車の開発者も「プリメーラは日本の消費者にとって足回りが硬いと感じるだろうけど、あの走りは魅力的だ」と率直にセダン系の開発力の負けを認めていた。
だが、相次ぐヒット車の登場があっても日進にとっての永遠の課題である販売力の弱さは相変わらず。初代モデルが素晴らしいスタートを切ったにもかかわらず、モデルチェンジを重ねるたびに「売れないモデル」が登場する「いつもの日進」を断ち切れない。ヒット車が持つ本来の魅力に目を向けず、目先の売れ行きを考える日進経営陣がモデルチェンジに介入し、2代目、3代目のモデルを平凡な車にしてしまうのだ。1966年に優秀な技術力を持つプリンセス自動車工業を吸収合併した後遺症もあった。合併は当時の通産省による産業再編の計画に沿う形で実現したが、日本の自動車草創期からの名門自動車メーカーである日進は、戦後生まれのプリセンス自動車の技術力を評価するものの、格下扱いしてしまうことがたびたび。プリンセス出身の開発陣が送り出す名車を否定してしまう。1970年代から日進の業績を支えた旧プリンセスが開発したモデルは次第に消えていってしまう。
しかも、バブル時代に合わせてヒットする車を品揃えして業績を下支えしたまでは良かったが、バブルが弾けた後に売る車がなくなってしまった。業績が悪化すれば、コスト削減の筆頭にあがるのが開発投資。開発力の低下はさらに売れる車の開発が遠ざかり、販売力の弱さからさらに売れ行きが低迷する。この悪循環から抜け出せない。世界に占める日進のシェアは1988年に6%程度だったが、98年には5%を切ってしまう。1ポイント程度の低下は自動車メーカーの損益分岐点を直撃、あがいても利益は出なくなってしまう。
日進自動車は経営不振の理由はわかっていた。優秀な人材は揃っている。愛知県が本社で生真面目で垢抜けない社風の織田自動車に比べて東京・銀座に本社を構え、日本の通商政策に深く関わるため「銀座の通産省」と呼ばれた日進だ。だから「日進の社員は自動車評論家ばかり」と揶揄される。訳知り顔で経営状況を説明し、克服する課題も明確にするものの、誰も火中の栗は拾わない。
日進の社長が無能だったわけではない。むしろ日本の産業界でも注目を集める存在感を持っていたのは事実だ。石井駿、久能裕らは識見と決断力が高く評価されてきた。とりわけ久能氏は経団連の会長に選ばれる寸前にまで行った。当時の経団連会長は東京電力の平岩外四会長。彼は早くからソニーの盛田昭夫会長を後任する考えが固まっていた。「世界の各国と貿易しなければ生きていけない日本。経営者は英語を駆使して世界とコミュニケーションできる人物でなければいけない」と考え、後任は盛田氏とかなり早い時点から腹を固めていた。ソニーの盛田会長は米国のメディアに英語でわかりやすく語りかける口調で高い人気を集め、企業ブランドに負けない輝きを発していた。何よりも、盛田氏の出身は平岩会長と同じ愛知県の常滑だった。平岩会長の常滑愛は並々ならぬものだった。しかし、不幸にも盛田氏は経団連会長決定寸前に急死。
後任には織田自動車の織田章太郎会長の名前が上がったが、平岩会長の評価は低かった。代わる人物として名前が上がったのが久能氏だった。販売シェアの低下や激しい労使関係などの難問に直面する日進自動車をかじ取りする力量に白羽の矢が立ったが、何せ会社の業績が悪い。経団連はカネと人が必要な組織。会長企業の負担は計り知れない。平岩会長は日進の体力では負担できないと最終判断した。結局、会長は織田章太郎氏に。「織田さんは若い頃から帝王学を学んでいるので、人の話を聞く力が優れている」と平岩会長の側近が解説してれた時にはその豹変ぶりに思わず笑ってしまった。
日進のプリンスと言われて1998年に就任した花輪良雄社長はもう疲弊していた。歴代の社長らを支えて早くから「将来の社長」と目されていた。米国工場の立ち上げなど海外経験も豊富で本社の経営企画部門で経営者の訓練も積んでいた。だが、社長に就任する前にすでに心身ともに消耗していた。
日進にとって凋落の根源は誰もが分かっていた。塩路一郎氏を頂点とした労組と経営の軋轢、あるいは馴れ合いは会社から活力を奪い、問題を見て見ぬふりをするのが「定年を全うする処世術」であった。銀座の通産省と呼ばれて自惚れていた会社が実は霞ヶ関の住人と同じ意識を持ってしまったら会社は終わりだ。日進は税金で生きているわけではない、自ら収益を上げなければ会社の存続はありえない。塩路氏の末期だったが私も取材のために銀座のクラブの前で立ちんぼをしていた記憶がある。「呆れてしまう」とはこのことか思い、「これも取材」と割り切って時間を潰したものだ。塩路氏を巡る労使の争い、会長、社長らによる主導権争いなどで日進自動車が奈落へ向かう様は多くの書籍で書かれている。改めて説明するのは字数を増やすだけと思い、ここで終わる。
「どんな大企業でも倒産するまでに10年間はかかる」ーー 取材経験から得た鉄則のひとつだ。特ダネを狙う新聞記者は、取材しながら目の前の優良企業が10年後どうなるかを考える。この会社の強さと弱点は何か、社長はじめ経営陣の力関係、社員・社内の雰囲気と意欲、オフィスや工場の清潔さなどを取材を通じて得た体内センサーによって計測する。3年後の業績などを予想するというよりも、このまま行けば3年後は伸びているが、5年後は転ぶ。この社長が続投していたら右肩下がりの左の道へ、もし経営の問題点を理解して改革に向かう社長が登場したら持続した成長に繋がる右の道へ、と読む。
1989年の時点で日産が近く倒産すると確信はできない。ただ、このまま変わらなければ3兆円を軽く超える倒産の悲劇が待っている。照準は1999年に合わせた。財務に詳しい人材らを加えて何年後の日進の姿を描く。結論は「3年持つのかどうか」。エッと言ってしまう答だった。
1980年頃から英国、フランス、ドイツの自動車メーカーは輝くばかりの歴史が負の遺産となり、経営は窮地に追い込まれていく。英国のランドローバーは日本のオンダと資本提携し、ドイツのAMWは創業一族が株式売却を日本の自動車各社に持ちけていた。ビートル自動車は日進と業務提携して日本でノックダウン方式の生産を始めた。成否を問わずに活路を探す動きが始まった。一方、日本の自動車メーカーは日米の自動車貿易摩擦に追われ、米社との提携、米国での現地生産などを最重要課題としていた。欧州との貿易摩擦を回避する欧州戦略の本格化はまだ先との認識だった。しかし、1990年代に入って明らかになった日進自動車の経営変調は世界の自動車再編の波を変える。日米が主役だった提携・合併に欧州が加わり、再編の方程式がより多元化した。言い換えれば、欧州メーカーが生き残りへ向けた解の一つとして米国、日本とどう組むかが問われ始めたのだ。
日進の変調はこれまで資本関係にも及ぶ。富士自動車が密かに願っていた日進グループから離脱できるチャンスととらえたのだ。それは誰もが日進自動車が生き残る保証はないと考えていた表れだった。実は最終的に日進と提携するルソー自動車は助けを求めた相手、織田自動車に断られた後、次の候補として交渉したのが日進ではなく富士自動車だった。織田よりオンダよりも低く評価され、規模が小さいグループ会社の富士よりも会社の将来を危ぶまれていたのだ。
バブル経済で華やかなヒット車を放った日進自動車の実相はすでにボロ布のように誰が見ても経営の綻びがはっきりと見えていた。気づいていたのか、気づいていなかったのか。日進は生き残りの迷路に入り込む。ばったり出会ったのがドイツ自動車だった。