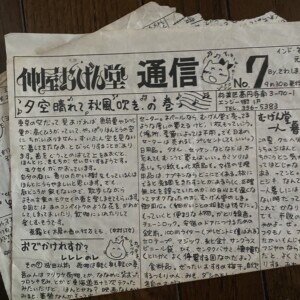阿佐ヶ谷の屋台、栃木屋の親父とお母さんと未明の一杯
ある晩、午後10時過ぎから飲み始め、朝の午前7時ごろまで寝ずに飲み続けたことがありました。初夏の過ごしやすい夜だったことも手伝って、阿佐ケ谷駅北口から帰宅する人の流れを見ながら時間が過ぎました。帰宅ラッシュはきっと午後7時ごろから始まっているでしょうから、午後11時過ぎから始まる人の波はその日のうち何度目かのラッシュアワー。
「ザクザク、ザクザク」。駅北口から帰宅する人が音を奏でながら溢れ出てきます。屋台から見ると、黒髪の人の束が駅の構内から長方形の厚紙のようになって出てくるように見えます。ぼっ〜と酔っ払って眺めながめていたら、毎夜この風景が繰り返されていることに気付きました。駅北口から厚紙の塊のように吐き出される人の波はそれぞれ昨日、今日、明日の物語を抱えて歩いていることにも気づきます。「俺は飲んでいるだけだあ、物語はない」。
夜10時から朝の7時過ぎまで屋台で飲み続ける
飲んでいる屋台のそばをチリンチリンとガラス音を鳴らしながら風鈴を売り歩く屋台が通り過ぎて行きます。「夏の風物詩かあ」という声がどこからか聞こえてきます。風鈴を買ってアパートの窓にぶら下げるのも風情があって良いなあと思ったのですが、風が強い日はうるさいだけ。風情も一緒に飛んできます。阿佐ヶ谷の密集したアパート街で、隣から喘ぎ声が聞こえる部屋に住んでいます。「近所迷惑だなあ」と瞬時に諦めました。
それから6時間程度過ぎると、朝の通勤時間が始まります。7時過ぎからは再び人の波が駅北口に飲み込まれて行きます。夜中とは逆の流れです。仕事に向かう人はみんな一晩の間に新しい物語が生まれたはずです。しかし、「俺はここで飲んでいただけだ」。新しい物語は今晩も屋台の長椅子にずっと座っていたぐらい。何かを見て聞いていたはずですが、記憶には残っていません。10時間以上も屋台一か所で過ごしてしまった自分の喉に乾燥した何かが胃袋から上がっているのを感じました。
そんな夜、というか夜明けが遠くに過ぎてしまった朝、屋台の店じまいが始まりました。店仕舞いを手伝って、親父さんと一緒にいつも屋台を駐車させる場所まで押して行きました。
そしたら、「家で一緒に飲むか」。親父が初めて誘ってくれたのでちょっと迷いましたが、栃木屋夫婦の家に行きました。アパートの部屋に入るといつものようにシャキッときれいな佇まいの着物姿で待っていた奥さんが鶏肉を煮ています。しっかり煮込まれた手羽先をお酒のサカナとして盛り付けてくれました。
屋台の店仕舞いを終えて朝からまた1升
親父は「飲もう」と茶碗を出します。ふと台所を見るとお母さんが洗い場に立っており、まだ洗っていない皿や鍋が積み重なっていました。その台所の縁を酔った目でもわかるでかいゴキブリが器用に渡り歩いて行きます。なんか日常の風景なのでしょう。お母さんは驚きもなにもしません。
目の間に並んだお酒も鶏肉の煮物も手が出せません。汚いからじゃないんです。徹夜仕事を終えて疲れているにもかかわらず、鶏肉を煮込んで一緒に食べて飲もうという親父さんとお母さん二人の気持ちが嬉しくてうれしくて酔えません。
3人でじっと畳の上に座っているだけです。とても手が出ません。親父さん、お母さんは何もいいません。私も言葉が出ません。「まあ、飲もう」。親父は一升瓶を持ち上げて湯呑茶碗に注いでくれます。この一声で一升瓶は空になり始めました。何を話したか、何を食べたか、そしてどう帰ったか覚えていません。
でも、台所の縁を渡り歩いていて部屋のどこかに居座っているゴキブリがデカかったのはよく覚えています。