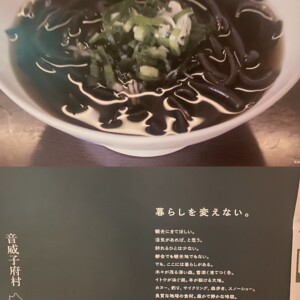釜島辺の「大人の恋物語」―今宵ロックバーで追憶に浸る―
猛暑の余韻が長引いたせいか、小さな秋を見つけるどころか、秋そのものも感じないまま冬を迎えた。木枯らしに吹き飛ばされた落ち葉が歩道をカサコソとなでていく街で、淡い恋心を抱きながら別の道を歩んだ男と女の物語を綴ってみたい。東京から京都へ、虚と実のあわいに二人が交わす言葉に感情を重ねていただければ幸いだ。(釜島辺)

懐かしい名曲に包まれて
2人は都内の隠れ家的ロックバー「Z」の扉を開けた……。大音響と熱気に包まれながら、紫煙が漂う薄暗いカウンターに並んで腰を下ろし、バーボンのグラスを傾ける。70年代さながらの空気だ。客のリクエストを巧みにさばくマスターが膨大なラックのLPレコードからピンポイントで1枚を取り出し、円盤に乗せていく作業にはよどみがない。はからずも懐かしいバラードが次々とかかり、男と女は懐旧に浸りながら、情感のこもったボーカルに身を委ねるのだった。半世紀前の名曲に耳を傾けながら、2人の鼓動を感じていただこう。
A Whiter Shade of Pale/Joe Cocker
ロック少年だった男の誘いで店に入ってすぐに流れたのはプロコルハルムのヒット曲「青い影」をジョー・コッカーがカバーしたバージョンである。枯れつつも艶やかな歌声が心に染み入る。
文学少女で、キャロル・キングが好きだった女も洋楽には詳しかった。学生時代には互いにLPを貸し借りした二人だった。ジャニス・ジョップリン、CSN&Y、エリック・クラプトン……。サウンドとともにあの頃の情景がよみがえる。
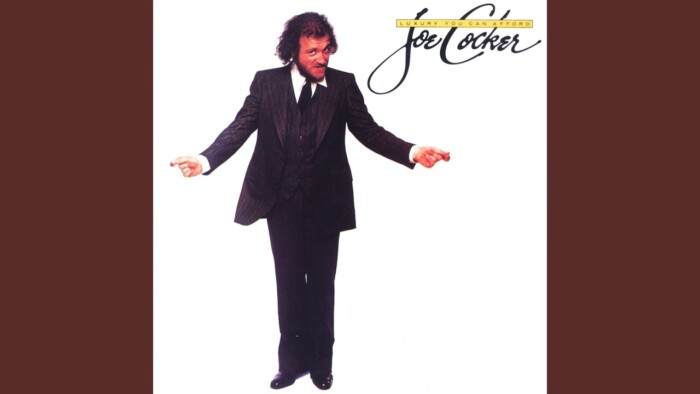
さて、ジョー・コッカーとくれば、ビリー・プレストンの「You are so beautiful」(美しすぎて)のカバーが知られるが、「青い影」は恋愛を超えたドラマ性のある名唱とも言える。ソウルナンバーで探せば、コード進行が似ているパーシー・スレッジの「男が女を愛する時」のイメージにも近い。
「荒井由実の『ひこうき雲』、覚えてる?」
「高校時代によく聴いたわよね。当時、新鮮だったわ」
「うん、あれは『青い影』にインスパイアされたって、ユーミンがラジオで話していたのを聞いたことがある」
「へえ、そうなんだ。たしかにバッハみたいな雰囲気が似ているわね……」
そんな会話が始まると、ハーパーのソーダ割りのグラスが2つ運ばれてきた。鋭くカットされた氷を包みながら琥珀色の泡が昇っていく……。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Me and Mrs. Jones / Billy Paul
「おっ、いきなりこう来るか」
「え、何か言った?」
言わずと知れた不倫ソングの代表格が流れてきた。カウンターの男は恥じらいを覚えながらも「よくぞかけてくれた」とほくそえんでいる。
「いけない恋だと分かっている。でも会いたい」。切なくも率直な心情を歌ったこの曲は、男女が夕刻にカフェで会うこと以外、年齢の差やそれぞれの立場など何も説明がない。罪を自覚した抑制的な歌詞なのに、それを越えようとするエモーショナルなボーカルが聴く側の心を揺さぶる。
グラスを手にした男が勝手にこの曲について想像してきたのは「白人のジョーンズ夫人を若き黒人青年が恋焦がれる姿」だ。それは黒人のソウルミュージックの背景にある社会が人種差別、公民権運動などと密接なイメージを観念的に植え付けられているからだろう。
2人は言葉を交わさず、ただ聴き入っている。三十代、四十代と会っていなければ、それぞれの感傷がもはや同じ軌道を描くことはない。しかし、どこかで引き合うのは二人が男と女だからである。
女は右膝の外側に、男の左膝がかすかに触れた瞬間、自分でも意外なほど胸の鼓動を感じた。
「なんなんだろう、ワタシ……」
とうの昔に冷却して忘れていた感覚ではないか。なぜ突然こんなところで……。そんな気も知らぬ男はまったりとした横顔を浮かべている。ネクタイを緩める男の仕草にゾクッとしてしまった女はそれを悟られないよう目を閉じ、乾ききっていた枯野が潤みだすのを愛しく感じるのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「Let’s Get It On/Marvin Gay」
《君と身体を重ね合わせたい。愛し合いたい。この思いをずっと抑えてきた。でも、もう我慢できない。今すぐ愛し合おう。生まれたままの姿で。人生の喜びを感じ合おう。もうじらさないで。僕のところにおいで。ひとつになろうよ……》
「やってくれますな」。男は心の中でつぶやいた。タイトルも歌詞もかなりは直接的。それでもソフィストケートされて聞こえてしまうのはさすが希代のソウルシンガー。そう言えば、この曲は彼を射殺した聖職者の父親を激怒させたのだった。
隣の彼女の瞳が潤んでいるように見えるのは男に酔いが回ってきたからだろうか。
たまらずに、2杯目のソーダ割りを注文する。
「わたしも同じにしようかな」
甘い追憶が芳醇な香りを心に広げているのは女の方もそうだった。そのしっとりとした声には確かな潤いがあった。大人の恋だから許されてしまうのか。もう細かいことはいいじゃないか。二人の影がそう語っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「New York State Of Mind/Billy Joel」
哀愁を帯び始めた中年が抱くニューヨークへの憧れに染みるピアノが聞こえてきた。日々何かが起こる大都市の鼓動を伝えるためなのかニューヨークタイムズ、デイリーニュースという新聞名が出てくる。
ビッグ・アップルと形容される大都会の喧騒と緊張の中で生きる男の感傷と決意が遠く離れた東京のバーにも伝わってくる。恋の舞台に大都会の夜はふさわしい。

グレイハウンドバスで故郷のニューヨークに戻ろうとするビリー・ジョエルは率直な心情をこのバラードに託して歌う。
≪I don’t have any reasons I left them all behind(理由はもう何もないさ。とっくに捨てたから)I’m in a New York state of mind(僕の心はニューヨークにあるんだ)≫
「そう、僕の心は君とともにある」
エンディングのサックスの音色を聴きながら、男は心の中で感じていると、彼女がふとつぶやいた。
「思い出しちゃうな……」
男はあえて反応しなかった。理由を問うのが無粋であるだけではなく、自分の知らない彼女の過去に嫉妬するのを恐れたからだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「You’ve Got a Friend/Donny Hathaway」
「このライブは凄い。悲鳴のような客の反応はハーレムの教会にいるかのようだ。神からから信徒(You)へ掛ける言葉なのだろう……」。男の鼓動が高鳴る。
《You just call out my name And you know wherever I am I’ll come running to see you again(あなたはただ私の名を呼べばいい。どこにいたって、私は走って、あなたにまた会いに行くからね)》
惜しくも自ら命を絶ったダニー・ハザウェイ、張りのある26歳の歌唱が素晴らしい。男と女の恋は神に通ずる壮大な愛の世界へと昇華されていく。
まるでマスターが「二人の恋に埋没するなよ。これが人類愛だ」と見透かしたように選曲したのだろうか。「やけぼっくりより、友情を確かめ合うだけでいいじゃないか」。抑制を求めるメッセージを歌に託したのだとすれば、さすがである。
2人は満ち足りた楽曲の余韻とともに店を出た。だが、遠い記憶の底から、満ち足りてない何かが沸き上がってくるのを2人はともに感じていた。
「ねえ、こんど京都に行かない?」
渋谷の雑踏の中で唐突に女が声を弾ませた。
「そうだ。京都に行ったら、ザ・バンドの『It Makes No Difference』を聴こう……」
男の心の中に、ふと切ないメロディーが流れた。
It Makes No Difference
(つづく)