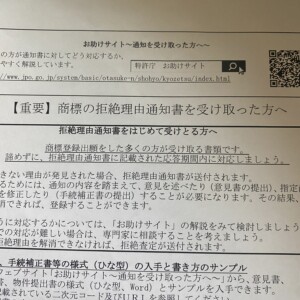南太平洋10 ラバウルで日本とニホンを感じる(その2)

ラバウル空港
パプア・ニューギニアのラバウルに到着しました。ラバウルといえば旧日本軍の航空隊基地を思い浮かべますから、なんの根拠もなくそれなりの規模の空港かなとイメージしてました。しかし、実際は滑走路の他には荷物検査など必要な設備をそろえた近代的な空港でした。自分でも何を期待していたのかわからないのですが、「ラバウルといえばラバウルでしょう」という誇大妄想が大きな空港を期待させたのでしょう。ところが手続きは結構、大変でした。
建屋に入り何気にスッと抜けてしまって良いかと勘違いしたら、スタッフに厳しく呼び止められて何度も荷物検査をしっかりチェックされます。羽田空港や成田空港のような入国手続きなどの関門がくぐり抜ける手間は不要と勝手に決めつけてしまい、「発展途上国」「小さな空港」と侮る内なる偏見を思い知らされたのを覚えています。ちなみに1994年、ラバウル近郊の火山が噴火しました。大量の降灰で街は埋れました。その後の復興の様子はわかりません。これから描く風景は、今も降灰に埋もれたままかもしれません。寂しいです。
ラバウル空港のそばにゴルフ場が!?

空港を離れるとすぐに現れるゴルフ場
空港を出発します。タクシーに乗って再びびっくりしたのはゴルフ場が見えてきたことです。最初は精気あふれるヤシの木の森に感動しました。葉の勢いの強さと輝きから緑色の露がボタリとこぼれ落ちるのではないかと思えるほどでした。これだけの濃い緑色のヤシの葉と輝きの強さを日本で見かけることがないと思います。育つべきところに育てば植物は全く異なるエネルギーを発するのですね。そのヤシの並木が連なる街道筋にみほれていたら、きれいにカットされた芝生が視野に飛び込んできました。これも内なる偏見です。ラバウルでゴルフ場があるわけがないと決めつけているので、目に映る風景が理解できないのです。草原がまるで人為的に芝のようにカットされているみたいと驚き続け、ようやくバンカーを見てハッと気づきました。そう遠くないところに活火山があります。火山灰が覆う土地を手入れしてゴルフ場にしあげたのでしょう。「ラバウルでゴルフ場かあ」。なんとも納得できないラバウルのイメージに葛藤している自分に気づき、自分自身に対しても違和感を持ってしまいました。
そして再び勝手な感傷から想像し描いていた街の風景と違った普通の街並みが現れます。当たり前のことを当たり前だと目の前に突きつけられます。第二次世界大戦が終わってから50年ほど過ぎています。日本が戦後末期の空襲で焼け野原となった街を新たに築いたように、パプア・ニューギニアのラバウルも日本に占領された歴史から解き離れています。戦時中、市街区はいわゆる碁盤の目のように整備され、近代的な都市として広がっていたそうです。現地の教育にも力を入れていたので、ラバウル周辺のココポ地域は高等教育を受けるため大学などに進学する子供が多く、国の発展に努めた人材を輩出したそうです。ちなみにラバウル現地に関する情報は内閣広報担当者から得たものです。学術的に証明されていたものではありません。また旧日本軍を礼賛する気もありません。
かじると赤い汁が出る実を探す。口の周りが赤く染まり、まるで・・・
訪れた街並みは確かに碁盤の目ような街区が残っています。ですが、パプア・ニューギニの他地域で見かける風景と同じです。ただ、今は亡き「アーサーアンダーソン」の看板を見つけた時は、世界展開を積極的に勧めていた米会計事務所がラバウルでも事業のタネを巻いているのには、それこそ舌を巻きました。
マーケットに行きます。到着すると、同行する内閣広報担当者が市場の多くの店をあちこち周り始めました。「何を探しているのか」と聞くと果実の一種だと言います。果実の名前は正確にはわかりません。タバコ代わりにガムのように噛んで楽しむそうです。その実を食べていると赤い汁が出てきます。噛み続けると、口内だけでなく口の周りも真っ赤に染まります。習慣性が強いのか、やめられないと苦笑しています。しかし、食している時の顔はなかなか野性的な風貌になります。
噛むたびに覗く白い歯は赤い色に染まり、実がまるで肉のような塊に見えるのです。まあ、焼肉を食べている感じです。そのためか「パプア・ニューギニア人が人を食っているようだと間違えられた原因の一つだよ」と彼はとても本気にするには危険過ぎるジョークを飛ばします。私も試食してみました。確かにタバコを噛むと滲み出る苦さを感じます。「ショートピースを噛むとこんな感じかな」でした。一度の経験で結構です。
マーケットはどこの街でも楽しい空間

いろいろな野菜や果物が並ぶマーケット
どこの街を訪れてもマーケットは楽しいです。現地の食生活、生きる力を肌で感じることができますから。「この野菜ってなんだろう」「どう料理するのだろうか」「このフルーツは甘いのかな、それとも苦いのかな」「ぎゃあ、この魚は見た目が派手でちょっと食えないなあ」。家族で食べているシーンを思い浮かべるだけでも驚きと感動の連発が続きます。
マーケットの現地の人も商売で店を構えているぐらいですから、私のような外国人にも遊び気分で声をかけてくれます。全然、言っていることがわからないのですが、「これ食べてごらん?」って感じです。「いや、食べ方わからないから無理だよ」。マーケットの店を縫うように歩くだけで、現地の空気に慣れていくのがわかります。
空港到着から夕方までの時間を使ってラバウル中心部の街を一通りまわりました。自分にとってラバウルは旧日本軍の歴史的象徴としか考えていないことを改めて気付かされました。現地に来てみると、「日本」は「ニホン」に変わっているのを思い知りました。もう半世紀近い過去です。明日は日本海軍の最大の拠点であった旧司令本部を行く予定です。それも、戦争遺跡の一つの見学と割り切り、今日も明日も歴史の本をなぞる一日と思い込んでいました。。
「中村軍曹にはお世話になりました」と日本語で声をかけられる
 しかし、それは早計でした。ホテルに着き、荷ほどきをしました。マラリアを媒介する蚊が怖いので、日本製の蚊取り線香を何本も燃やします。部屋が白い煙で充満するほどでしたが、それでも安心できません。ホテルのスタッフには申し訳ないと思ったのですが、マラリアだけは手を抜けません。しかも敵は見えません。怖いです。
しかし、それは早計でした。ホテルに着き、荷ほどきをしました。マラリアを媒介する蚊が怖いので、日本製の蚊取り線香を何本も燃やします。部屋が白い煙で充満するほどでしたが、それでも安心できません。ホテルのスタッフには申し訳ないと思ったのですが、マラリアだけは手を抜けません。しかも敵は見えません。怖いです。
夕飯までのわずかな時間をホテル界隈を散歩しようと外に出たら、老齢の男性が日本語で話しかけてきました。「戦争中は中村軍曹にお世話になった」。日本軍に占領されていた南太平洋の島嶼国では日本語を話す人がまだ多いです。年齢から見て小さい頃に日本語教育を受けたのだと察しました。ちょっと雑談してみようと思い、「いつ日本語を習ったのですか」と聞き返しました。
彼は戦争中、日本軍の兵士らの世話をしたそうです。「すぐにぶん殴る兵隊もいたが、中村軍曹は私を守り、可愛がってくれた」と続けます。一気に50年前の時間に戻されます。「日本」はもう歴史と割り切った自分の前に突然、かつての「日本」が現れました。