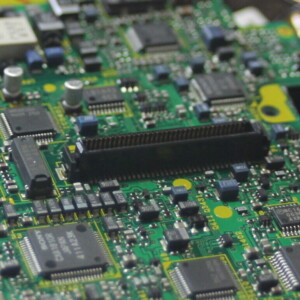ほぼ実録・産業史 ⑥ 独ビートル自動車は老獪?融通無碍?守りにも攻めにも強い
AMW、ドイツ自動車と書き続けたら、やはりビートル自動車に触れないわけにはいかない。
長年、自動車産業を見ていて感じるのはビートル自動車の存在感だ。異色、いや違和感というのが正解かもしれない。ドイツの他の自動車メーカーを含めて仏、イタリア、英など欧州の自動車メーカーと比べ、身にまとう空気が違う。「ビートル」「ゴルファー」という不世出の小型車を開発し世界的なヒット車としての地位を守りながら、常に日本の織田自動車と世界一の生産台数を競う実力は素晴らしい。フェラリーやポルシェのようにブランド名を聞けば誰もが無口になるクルマを揃えているわけではないが、操縦安定性や顧客満足度などの基本を高い水準で守っている。
欧州の自動車産業はイタリアのカロッツェリアと呼ばれる工房をイメージするランボルギーなどが根強く生き残る一方、AMWやドイツ自動車のように高級車から小型車までを扱う量産型のメーカーが併存する。ビートルはなぜか日本車メーカー、とりわけ織田自動車の経営と二重写しに見えてしまう。ドイツ、欧州の自動車メーカーとして捉えにくい。なんとなく個性が薄いが、強く主張しないのが個性と笑いながら融通無碍に生き残る世界の強者だとようやくわかってきた。
ビートル自動車と日本との付き合いは長い。ドイツ自動車やAMWが床の間に飾られるクルマだとしたら、その辺に一緒に並ぶ日本車メーカーの仲間と見えてしまう。
だからというわけではないが、20世紀末からのビートル自動車の経営戦略は日本から眺めた方がわかりやすい。ビートル自動車は1953年にヤナセが輸入を始め、右ハンドルなどの日本のクルマ事情に合わせた仕様に設定し、常に輸入車といえばビートルという評価を固めた。カブトムシの愛称で呼ばれた独特の丸い背中をしたデザインは大人気を集めた。ちなみにヤナセといえば梁瀬次郎さんを抜きに語れない。場を改めて一度ヤナセの梁瀬次郎さんのことは書きたい。日本で最も人気の高い経営者の一人、鈴木修さんとタイマン張れるのは梁瀬次郎さんしかいないだろう。申し訳ない、品が悪い言葉を使ってしまった。
話は戻る。ビートル自動車は1983年に日本販売会社を設立し、独自の販売力を拡大する。1991年に織田自動車がビートル自動車の販売を始め、1992年にはヤナセはビートル自動車との販売契約を解消する。ビートルと織田自動車の巧妙な販売戦略の思惑が一致したのだ。織田自動車ー1990年代の織田系列販売会社はバブル経済の大波に乗って儲けに儲けていた。そこで、織田本体はいかに利益を吐き出させるかを考えた。全国の販売会社、系列部品メーカーなど織田自動車の血脈ともいえるネットワークを押さえていた当時の児島正織田自動車副会長が教えてくれた。「販売会社が儲けすぎると、妙なビジネスに手を出す。株取引や不動産などで不祥事を起こされると困る。過去、織田の指示に従わずに手を染め、経営破綻することもあった。儲かっている時は販売会社の利益を吐き出させること大事なんだ」。実際、系列販売会社の不祥事が相次ぐ。
その相手としてビートル自動車をなぜ選んだのか。日本の自動車市場は輸入車のシェアが1割程度と推移していたため、海外の自動車メーカーからは閉鎖的だと批判されていた。米国車は燃費が悪いので、売ろうにも売れない。織田自動車が組んでも将来に支障をきたさないのは、日本市場に骨を埋めようと本気で取り組んでいるドイツのビートル自動車しかなかった。ドイツ自動車やAMWはドイツの誇りが強すぎていつかは衝突する。ビートルならトヨタの車種構成ともろに競合しないし、「話ができる相手」(児島副会長)だ。しかも、織田系列店が販売しても、さほど売れないのがわかっている。「多少損してもらう方がありがたいし、そうなるはず」と児島副会長は好きなお酒を飲みながら明かしてくれた。両社の販売提携は2009年に自然消滅した。
実は織田自動車は1989年に提携して小型トラックをドイツと日本で生産している。織田が米国市場で販売しているピックアップトラックをモデルに生産し、バッジを張り替えただけ。コストはかけていない。ほとんど売れていないので知られていない。それで良いのだ。オンダや日進自動車に出遅れた欧州での自動車現地生産、とりわけ欧州大陸やドイツ、フランスへの経済貢献するという欧州の各政府への政治的なアピールが主眼だったのだから。こちらも1996年に終了している。
ビートル自動車も同じだ。日本の有力自動車メーカーとの関係をテコに日本、アジアの市場に地歩を固める戦略だった。相撲に例えればがっぷり四つに組む必要はない。日本の政府と自動車各社と信頼関係を築き、懐に入ることが最大の目的だからだ。織田自動車との生産・販売の提携に先立つ1981年、日進自動車と提携し、中型車「サンタモニカ」を日本国内で生産することで合意した。1984年から神奈川県の工場でドイツから主要部品を輸入して組み立てるノックダウン方式を開始、販売も始めた。日進自動車にとってビートル自動車の車体生産技術の習得などを期待したが、ビートル自動車にとっては「サンタモニカ」の販売拡大とともに、アジア市場をにらんだ一手だった。同車の販売はさほど伸びず、共同生産は1991年に終了した。日進に続いて織田自動車との共同生産、販売は自然な流れだ。ビートル自動車のカール・ホーン会長がフランクフルト・モーターショーで語った「日進とは互いの信頼関係を充実させながら、提携の中身を充実させていきたい」と差し障りのない発言の裏には、付かず離れずの日本戦略が隠されていた。
日本の経験がアジアでフルに活きたのが中国。ビートル自動車は1984年に中国・上海で合弁会社を設立して「サンタモニカ」の生産を開始した。確か1日75台程度の生産台数だと思った。この台数で生産効率とか採算を考えたら割は合わない。だがビートルは生産した。その生産方式が奮っている。現場を見ていないので断言できないのが残念だが、視察した自動車メーカーの人間によると、ベルトコンベヤーを設置するほどの投資を必要としないので、丸太の上に溶接した車の骨組みを載せてゴロゴロと音が聞こえるような感じで一台一台にエンジンを搭載し、部品を組み付けていたそうだ。(映画モダンタイムズの世界ですよ」と苦笑する。当時、ビートル自動車に取材を申し込んだが、現場は見せれられないと断られた記憶がある。
1980年代の中国の自動車生産は草創期。ビートル自動車の涙ぐましい献身は、中国政府の心に響く。日本車も含めて中国の自動車生産には二の足を踏むのがほとんどの時期。他に先んじて日本市場でため込んだ市場の治験を中国市場に投入した。「サンタモニカ」が上海で多く見かけ、その後の中国政府の上層部も含めてビートル自動車やグループ会社のオウディが高級車として採用されているのは、丸太の上で自動車を生産したあの日があったからだ。米国では現地生産しても失敗を重ね、現在は工場を持っていない。中国政府、手強い交渉が欠かせない合弁相手と深く関係を構築できたのは日本での経験があったからといえる。ビートルがトヨタと世界第一位の生産台数を競う今があるのも、中国市場の存在が大きい。それがドイツが中国のアジアやアフリカなどでの政治・経済そして人権などの問題で二の足を踏ませる要因になっているのも見逃せない。
政府、当地の自動車メーカーと手を組み世界一位を競い合う規模にのし上がったビートル。しかし、新技術の研究開発のトップランナーではない。ワールドカーの発想を取り入れたエンジンなど基幹部品を共通化してまとめて組み立てるモデュールといった考えで生産コスト削減の先駆的な地位を得ていたが、排ガスなど環境技術でトップではない。
ガソリンエンジンの分野では日本などに勝てないこともあり、欧州はディゼールエンジン主体の環境技術で日本車を締め出そうとした。欧州は実力勝てないとなると、制度や基準つくりを変えて欧州、自国の優位性を取り戻す。エンジン技術も同じだった。しかし、「ディーゼルも含めて技術開発に投資を続けていたのか?」という素朴な疑問は消えなかった。
2015年9月、米国の環境保護庁がビートル自動車によるディーゼルエンジンの排出規制の不正を発表した。ビートルの信頼感は一気に低下し、存続の危機に追い込まれる。しかし、結果、乗り切った。ディーゼル不正が発覚する以前からビートルの技術力では生き残れないと考えていたが、現実に発生した不正事件を乗り切ったしたたかさを考えると、「100年に一度」と言われる電動化の嵐に襲われる世界の自動車産業のなかで、ビートルは確実に生き残る一社に選ばれる。
日本の軽自動車メーカーであるサトウと提携したのも、未来の自動車を軽の可能性を考慮した。ビートルにとって日本車との提携は不可欠だったわけではない。しかし、目の前に利用できるものは利用するのだ。冷徹な判断が下さられただけだ。サトウの中興の祖である佐藤進もこれまで米国のUS自動車などを手玉にとってきた自らの提携の経験からビートルならうまく手玉に載せられるだろうと思ったはず。ビートル自動車もサトウぐらいは巻込めると踏んのだ。どちらも嵌めたと勘違いしたのが破綻の結果を招いたのだが、その後の経営に及ぼした影響は軽微だった。
地球環境問題で世界の産業規制が大きく変わるのは必至だ。自動車に限らず企業がビートル自動車のしたたかさに学ぶことは多い。