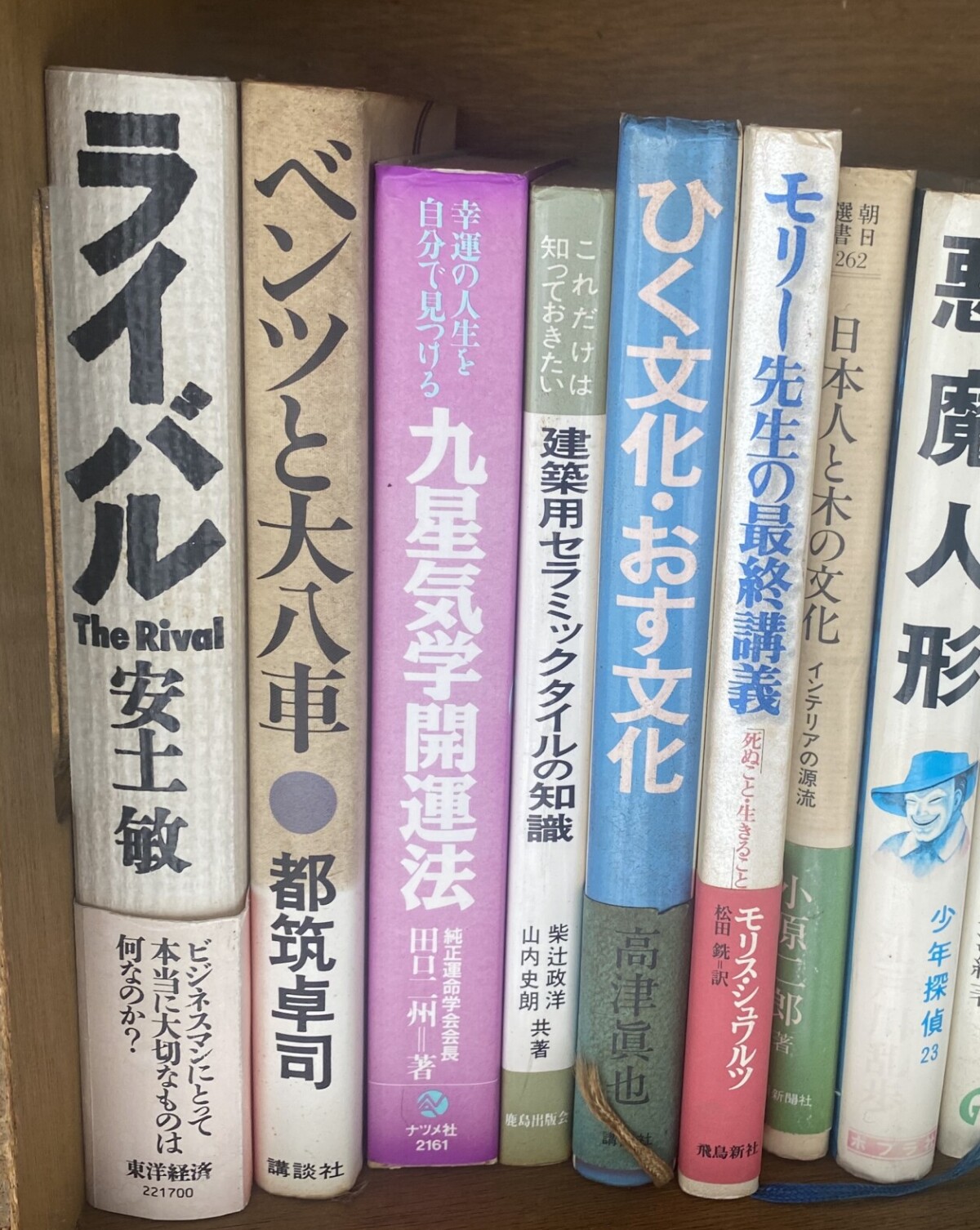
ほぼ実録・産業史 自動車編 ⑤ 「セルジオ」の凄さ、日本車の「ガラスの天井」も照らし出す
ドイツ自動車のシュツットガルト工場建屋に驚くべきフレーズを書かれた看板が掲げられた。
「この車はわれわれを超えている。この車に負けるわけにはいかない」
シュツットガルトの工場では一台の車が解体され、徹底的に研究されていた。織田自動車の「セルジオ」だった。この車は1989年、米国市場の高級ブランド向け車種「レグザス」として開発された。しかし、日本はバブル景気の真っ盛り。万年2位の日進自動車は高級車「ジーマ」を投入して大人気を集め、「ジーマ現象」とまでいわれるブームを巻き起こしていた。織田自動車は日本市場に合わせた味付けを加えて「セルジオ」を開発して「ジーマ」への対抗車種として発売したのだ。織田自動車はもともと石橋を叩いても渡らないどころか石橋を叩き壊してしまって渡れないといわれるほどの社風。競争相手と認識したら、徹底的に研究する。それが木を見て森を見ずに例えられるようにそれぞれのクルマは素晴らしいのに全体の車種構成としてのバランスが崩れ、総合的なブランドを高める力にならない弱点を抱えていた。
だがセルジオは違った。日本市場向け専用なのでジーマを競合車種として視野に入れながらも、高級車のデファクトスタンダード(事実上の業界水準)であるドイツ自動車を見据えて練り上げた。日本のライバルであるジーマはインテリアなど高級感を醸し出されているものの、基本はオーナーがドライバーシートに座って運転して楽しいと感じるクルマに仕上がっている。日進がライバルと目する織田自動車を代表する「キング」に比べてサスペンションは固めに設定し、ドイツの自動車メーカーが築き上げた高級市場に迫るテイスト(味付け)を吸収して日本市場向けに仕上げた。
織田自動車の高級車といえば「センチュリオン」や「キング」があるが、オーナーは後部座席に座ってクルマを味わう。運転席にはプロのドライバーが座る。プロを雇用できる資力を持っていることを見せつける。それが日本の高級車のブランドを生み出す源泉だった。運転そのものを楽しむ欧米の基準と異なる織田特有のワールドに没入していた。後部座席にはなんでもあった。マッサージ機能を備えた車種も。日本を訪れたドイツ自動車の技術者が後部座席に座り、何気なくマッサージボタンを押したら予想もしないシートの動きに驚き、飛び上がったそうだ。排気量3000cc級のキングは日本国内のブランドとして「いつかはキング」といわれるほど購入する人間と出世あるいは肩書きを二重写しにするクルマになった。だから運転を楽しむ富裕層はこぞってドイツなど欧州から輸入したクルマを購入してしまったのかもしれない。
しかし、それは日本だけの話、世界には通用しない。キングは日本と似た性格の市場である中国に輸出されたことはあるが、世界に輸出されない、いやいや輸出できないクルマだった。北米や欧州には日本車が入り込めない高級車市場がある。織田や日進自動車は日本の高級車市場を牛耳っていたが、両社の高級車は北米や欧州でまったく太刀打ちできない。オンダがオンダに続く第二ブランドとして「アキラ」を投入していたが、高級車の一歩手前までしか近づけていなかった。織田も「オダ」に続く第二の高級ブランドとして「レグザス」を創り1980年代後半に投入したが、その評価は発展途上の段階だった。
ゼルジオは日本車の前に立ちはだかる壁をぶち破った。ドイツと日本のテイストを丸ごと飲み込み、基本性能を世界水準に引き上げながら他のメーカーが追随できないクルマの世界を築くことに成功したのだ。走りなどクルマの基本性能は世界初の電子技術を存分に使ったサスペンションなどでドイツ自動車に引けを取らない水準に達する一方、運転席を包む空間の設計ではいわゆる「かゆいところに手が届くクルマ」が誕生した。車内は日本のユーザーが最も関心が高い静寂性を極め、「エンジン音が聞こえないので、運転していても不安になる時がある」と冗談が出るほどフロントからのエンジン音は抑えた。エンジン音の違いをクルマの個性でありブランドと捉える欧州の常識を覆す発想だが、その後の欧州高級車が「静粛音」を競う潮流を生んだ。
自動車メーカーはどこも新車を解体して徹底的に勉強する。織田もドイツ自動車を解体、研究している。ドイツ自動車に勝てないのは機械技術力と経験に裏打ちされたノウハウであることは以前からわかっていた。これは織田だけではない。日本車すべてに通じる宿命だ。100年以上の年月をかけて自動車を発明して進化させた欧州の自動車メーカーならではの強みであり、その結晶が高級車である。日本は「100年間の歴史」を電子技術力で買うことにした。1980年代、日本の電子機器メーカーは世界の最先端に向けて突っ走っていた。米国で発明されたコンピューター、電機部品、特に産業のコメといわれた半導体については市場シェアは5割も占めていた。日本の電子技術と部品は欧米と闘える水準にあった。
日本の電子技術が自動車の未来を機械の塊から電子技術の塊へと加速したのだ。しかも織田の系列部品メーカーには織田ゼンソーがいる。ゼンソーが自動車部品の電装品を主に生産しているが、その技術力は世界最高といわれるドイツの総合自動車部品メーカーであるロバート・ボッシュに迫る勢いとなっていた。マイコンやメモリーなど半導体を自社で生産するなど自動車部品の技術力は親会社の織田系列から飛び越え、ロバート・ボッシュに並ぶ世界の自動車部品メーカーを目指していた。織田はゼンソーが親会社の指示通りに電子部品を生産したため、巨額を投じて半導体工場を建設して牽制したことがあるほど。織田のある副社長は嘆いていた。「1000億円もかけて脅しをかけないといけないんだからね」。実際、織田系列の自動車部品メーカーは日本の自動車産業の中でいずれも群を抜いている。アシセンなど経営情報は最小限公表するが、技術開発などは外部に公表しない硬い殻に閉じこもっている系列メーカーが多く、世間に知られていないだけだ。
日本のクルマは欧米を追いかけ、キャッチアップして米国は追い抜いた。セルジオで高級車の高みに手が届きそうな自信を持ったのは事実。しかし、そこから先の高級車の頂上には手が届かない。マーケットが大きい大衆車を作り続けた日本車の宿命なのかもしれない。織田自動車の歴代の開発担当役員が本音を漏らしてくれたことがある。1980年代の金田太郎専務は織田と常に争ってきた日進自動車についてデザイン、性能が優れているのを率直に認めた上で、「織田はデザインでは勝てない。だからうちの強みを耐久性に求めることにした。どんなに走ってもエンジンは壊れない。だからまずタクシーでの採用比率を高め、長持ちすることを示した。そうすれば織田の自動車は丈夫だと多くの消費者に知ってもらえる」。真面目一本槍で「三河の田舎者」と揶揄する声が出ても、この伝統は変わらない。地球上最も過酷な地域でも厚い信頼を獲得している「ランドマーククルーザー」を世界的な大人気のヒット車に育てた力の根源でもある。
クルマもバブルに、日本車の限界も見える
1990年代のバブル期、バブルの象徴とも言われた車種を相次いで発表し、ヒットさせた吉田和夫専務は苦笑が止まらなかった。「どんどん新技術を加えていったら、なんでもできるようになる。そうなると車重が重くなるのでターボやスーパーチャージャーをつけてスポーティーさを高める。気づいたらクルマまでバブルになってしまった」。織田自動車は極めることでは頂点に立った。しかし、「無駄なもの」をいかにも「貴重なもの」に感じさせる欧州のブランドの極意は体得できなかった。ドイツ自動車が驚愕したセルジオは世界の頂点に立てる日本車の可能性を示したが、その限界も示したのだ。セルジオは織田が北米のレグザスブランドを日本国内でも展開するため、2006年にレグザスに統一される形でその役割を終えた。
そういえば私の世代でセルジオといえば思い付くのはブラジルの音楽家であるセルジオ・メンデス。彼は「マシュ・ケ・ナダ(Mas Que Nada)」を世界的にヒットさせたが、Wikipediaなどによると当時のサンパウロのスラングで「勘弁してよ」「なんてこった」「やなこった」という意味で使われたそうだ。ドイツ自動車なと高級ブランドを自負していたメーカーにとって、セルジオはまさにマッシュケナダ。日本の自動車メーカーが自分たちが真似しないといけない車を開発するとは・・・。ただセルジオ以後、日本が高級車のデファクトを創り出すことはできなかった。日本の産業すべてに共通することだが、世界の最前線あるいは頂点に立つと「これからどうすれば良いのか、わからない」と悩み立ち往生してしまう。セルジオの輝きは日本車の未来を照らし出してはくれなかったのだ。キラリと輝いて見えたのは、日本にとっての「ガラスの天井」だった。






